はじめに:AIは行政書士を奪わない、ただ“選別”する
「AIが行政書士の仕事を奪うのでは?」
「契約書の作成なんて、もうChatGPTで十分なんじゃないか?」
──そんな声をよく耳にします。
たしかにAIの進化は目覚ましく、契約書のドラフト、文章校正、条文検索といった作業は数秒で完了します。
しかし同時に、多くの行政書士が気づき始めています。
「AIをうまく使える人」と「AIに使われる人」との差が、確実に広がっている。
AI時代に消えるのは“人間の手”が不要な作業。
逆に、生き残るのは“判断・調整・信頼構築”という、人にしかできない仕事です。
本記事では、「AIを敵ではなく味方につける行政書士」になるための実践戦略を、実際の活用例とプロンプト(AIへの質問例)を交えて徹底解説します。

第1章:AIが得意なこと・不得意なことを見極めよう
AIは確かに優秀ですが、万能ではありません。
その“得手・不得手”を理解することが、最初の一歩です。
✅ AIが得意な領域
- 定型文書の作成(契約書・申請書など)
- 誤字脱字のチェックや文法修正
- 条文・通達の検索や要約
つまり、「誰がやっても同じ結果になる仕事」はAIが得意です。
⚠️ AIが苦手な領域
- 依頼人の感情や事情を踏まえた法的判断
- 行政庁との調整や“非公式なルール”の確認
- リスクとリターンを整理した最終決定
AIは情報を処理できますが、責任を取る判断はできません。
だからこそ、行政書士は「AIの結果をどう使って最適解を導くか」が価値になります。
第2章:AI時代に行政書士が磨くべき3つの“技術”
従来の記事では「聞き出す力」「つなぐ力」「判断力」と表現されがちですが、
AI時代に通用するのは、それを“技術”として体系化できる人です。
① リスク言語化技術(判断力の再定義)
AIは複数の選択肢を出すことはできます。
しかし、依頼人の「感情」や「事業の方向性」を加味して最終的に選ぶのは人間です。
例: ChatGPTが「契約解除条項」を3案出したとします。
行政書士はその中から「依頼人のリスク許容度」や「取引先との関係性」を考慮して、最適案を選び、法的根拠とリスク説明を添えて提示します。
これが、AI時代の「判断力」です。
AIをただの生成ツールではなく、“選択肢の土台”として扱う訓練が必要です。
② 情報獲得技術(現場のリアルを掴む力)
行政書士の現場では、同じ申請でも自治体によって運用が異なります。
この“ローカルルール”を把握する力こそ、AIでは再現できません。
例:「建設業許可の更新手続きで、都道府県ごとに必要な添付資料が違う」
→ 事前にAIに「東京都の公式要領を要約して」と頼み、下準備をしてから窓口で確認。
その場で得た“非公開ルール”を次に活かせば、他の士業にない強みになります。
つまり、AIで情報の下ごしらえをし、人間の足で差をつける。
これが現代の「情報獲得技術」です。
③ 対話設計技術(ヒアリングの構造化)
AIが最も苦手とするのは「相手の本音を引き出すこと」。
依頼人は、法的に必要な情報を必ずしも自覚していません。
行政書士の仕事は、依頼人の“雑談の中のヒント”をAIに再質問して、
法的に整理するプロセスをデザインすることです。
例:「お父様の遺言書がなくて揉めてる」と相談されたら、
ChatGPTに「相続争いが起きやすい典型パターンを5つ教えて」と聞き、
依頼人に「今の状況はどれに近いですか?」と尋ねる。
このようにAIを“質問のきっかけ生成装置”として使うことで、
ヒアリングの精度が格段に上がります。
第3章:AIを“時短ツール”ではなく“差別化エンジン”に変える実践法
AIを使って作業が速くなるのは当たり前。
これからは、“AIを使ってどう差別化するか”が勝負です。
🔹 戦略1:AI-Assistedサービス商品化
「AI+人間のダブルチェック」を売りにするだけで、顧客の信頼度が跳ね上がります。
例:
ChatGPTで契約書を作成 → 行政書士が人間の目でリスク評価 →
「AI分析レポート+専門家レビュー」として納品。
AIを使ってスピードと網羅性を高め、人間が最終判断で付加価値をつける。
これがAI時代の新しい行政書士の仕事設計です。
🔹 戦略2:プロンプト(質問設計)でAIを味方にする
以下は、実際に行政書士がAIを使う際に役立つ質問例です。
学習フェーズ(受験・勉強中)
行政手続法第3条の趣旨を、行政書士試験対策用に200字で説明。
この条文が過去に出題された年度も一覧にして。
実務フェーズ(書類作成・調査)
東京都の飲食店営業許可申請に必要な添付書類を、2024年度版の公式要領に基づいて整理。
引用元URLも明示して。
差別化フェーズ(顧客提案・集客)
建設業許可の申請代行サービスをAIで効率化した場合の提案書フォーマットを作って。
「AIによるリスク分析」を組み込みたい。
プロンプトの精度が上がるほど、AIは“実務パートナー”になります。
つまり、「AIにどう聞くか」こそ行政書士の新しいスキルです。
第4章:体験談──AIで合格した人、AIで顧客を増やした人
🧩 受験生Yさん(40歳・会社員)
Yさんは通勤中、スマホでChatGPTに条文や判例を質問。
「行政手続法第14条のポイントを3行で説明」「過去問で出やすい点を整理して」と入力。
AIの要約をもとに、自分の言葉で再説明するトレーニングを繰り返しました。
「“AIに説明できるほど理解する”を目標にしたら、記憶が定着しました。
学習時間は短いのに、模試の点数は着実に上がりました。」

🧩 開業行政書士Kさん(45歳・独立3年目)
Kさんは契約書の初稿をChatGPTに作らせたあと、自分でリスク項目を加筆。
さらに、AIが検出したリスクを依頼人に「AI分析結果レポート」として可視化して提出しました。
「“AIも認めた提案書”としてクライアントの信頼が高まりました。
単なる時短ではなく、サービスの説得力が増したんです。」
その結果、競合他社より単価を上げても成約率は上昇。
「AIを付加価値に変える」ことが、Kさんの武器になりました。
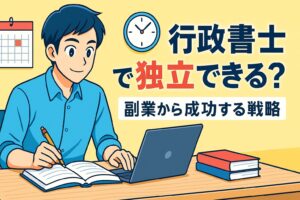
第5章:AI学習を支える通信講座とツール活用法
AIを活用する行政書士を目指すなら、学習段階からAIを取り入れるのが効果的です。
🔹 資格スクエア行政書士講座
AIによる「弱点診断」で学習が循環する
森T講義とAI演習機能を併用することで、理解不足の箇所をAIが自動的に提示。
効率的に「わからない」を潰せます。

🔹 スタディング行政書士講座
スマホ1台で学べるAI講義サポート付き。
講義動画を見たあとに「ChatGPTで要点を質問→自分で再説明」という
“理解の循環”が最短で作れます。
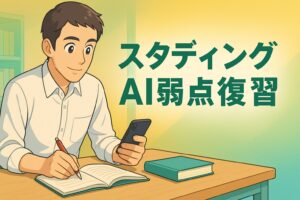
🔹 フォーサイト行政書士講座
過去問AI分析ツールを搭載。
苦手分野を自動で可視化し、学習効率を最大化。

第6章:結論──AIが答えを出す時代に、人が“決断”で価値を生む
AIが進化すれば、誰でも書類を作れるようになります。
しかし、「どの答えを選ぶか」「なぜそれを選ぶか」を説明できるのは人間だけです。
行政書士の真価は、
AIが生んだ“可能性の中から、依頼人に最適な一手を決断する力”にあります。
だからこそ、AIは行政書士の敵ではなく、“判断力を鍛える最高の相棒”です。
💡 今日からできる行動ステップ
- ChatGPTを開いて、「行政書士としてAIで何ができる?」と質問してみる。
- 出てきた答えを、あなたの言葉で再構成してみる。
- その瞬間、あなたは“AIを使える行政書士”への第一歩を踏み出しています。
👉 次に読むべき関連記事



まとめ
AI時代に成功する行政書士とは、「AIに代わられない人」ではなく、
「AIを使って誰よりも速く・深く・正確に考えられる人」です。
資格を取る目的は、AIと競うことではなく、AIを味方にして自分の強みを広げること。
今日から一歩、AIとともに未来の行政書士像を形にしていきましょう。
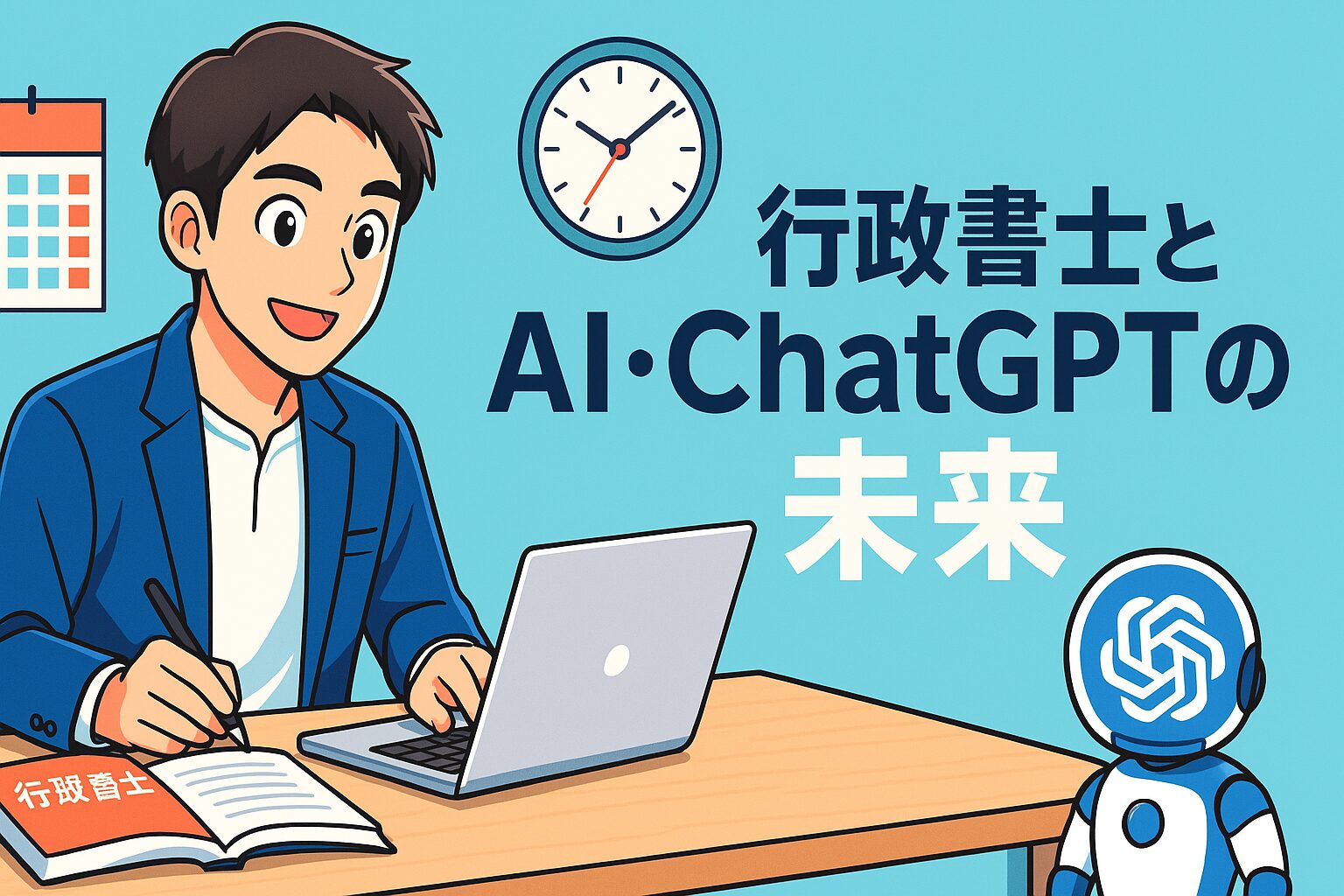
コメント