— 40代・多忙な社会人でも“効率重視”で合格点に届く実践メソッド —
「行政法が難しくて、なかなか点数が伸びない」「40代からでも本当に合格できるのだろうか」。
こうした悩みは珍しくありません。けれども事実として、行政書士試験における最大の得点源は行政法です。配点の観点からも、学習の再現性という意味でも、最もコスパよく点数を積み増せる科目が行政法です。
行政書士試験の全体戦略(配点・優先順位・回し方)を先に整理したい方は、こちらの記事からどうぞ。
行政書士試験における行政法の重要性(配点の事実)
| 科目 | 出題数 | 配点(目安) |
|---|---|---|
| 憲法 | 約5問 | 約20点 |
| 民法 | 約9問 | 約36点 |
| 行政法 | 約19問 | 約76点 |
| 商法・会社法 | 約2問 | 約8点 |
| 一般知識 | 約14問 | 約56点 |
→ 行政法だけで全体の約4割。 ここを安定させれば合格のボトルネックが解消され、合計点が一気に伸びます。
結論
行政法は「条文→判例→過去問」の三位一体で伸びます。
さらに“やらないこと”を決める捨てる戦略と、記述式(40点配点)に直結する60〜120字テンプレを併用すれば、短時間で合格点に到達できます。
秘訣1:条文知識の基礎固めを徹底する(3法を最優先)
行政法は条文の理解が命です。特に行政手続法・行政不服審査法・行政事件訴訟法(学習上は「手続」「不服」「救済」と略称で把握)を最優先の柱にします。
効率的な学習ステップ(条文編)
- 頻出条文から着手:直近10年の出題で繰り返された条文を優先。
- 「趣旨」を1行で言えるか確認:条文の存在理由が腹落ちすると応用が利く。
- 条文番号もセットで覚える:択一のスピードと正確性が上がる。
- 条文→短問演習→条文に戻るの往復で“当てはめ感覚”を作る。
ポイント:条文の定義・手続・期間・主体は、選択肢のひっかけの根拠になりやすい。暗記は「言える化(口に出して説明)」が定着の近道です。
秘訣2:判例は“頻出パターン”に絞り、言い換えに耐える
行政法は判例問題の比重が高いですが、すべて網羅する必要はありません。定番論点のパターン化が最短ルートです。
頻出判例(例)
- 行政行為の取消し(瑕疵の承継、取消訴訟の要件 等)
- 裁量権の逸脱・濫用(統制基準、審査密度)
- 不服申立てと訴訟の関係(先行手続・審査請求の可否)
- 処分性・原告適格(処分性の判断枠組み、法律上の利益)
- 国家賠償法(公権力の行使、違法性の判断枠組み)
回し方(判例編)
- 1論点=A4で要旨→基準→結論→当てはめ例に縮約
- 言い換え耐性:本文を別表現で言い換え練習(自分の言葉で言い直す)
- 一問一答とカード化:1日5枚でも**「毎日触る」**
頻出7割主義:出題の多くは定番判例の言い換え。新規判例は直前期に一覧確認で十分。全部やるより毎日回すほうが合格に近い。
秘訣3:過去問で“出題パターン”を体得(直近5年×3周)
行政法は出題形式が安定しており、過去問演習が最強です。
学習サイクル(標準)
- 本番形式で解く(時間を測る)
- 解説で「なぜその結論か」を言語化(根拠条文・判例基準をメモ)
- 弱点をテキスト・条文に戻って補修
- 1週間後に再度解く(記憶の再固定)
| 周回数 | 正答率の目安 | ねらい |
|---|---|---|
| 1周目 | 40〜50% | 出題の型と頻出論点の把握 |
| 2周目 | 60〜70% | 根拠の言語化が進む |
| 3周目 | 80%以上 | 取りこぼしの最終修正 |
注意:過去問は「覚える」ためだけでなく、本試験の問い方に身体を慣らすための訓練。設問文の仕掛け(否定・二重否定・比較)を読む技術も鍛えます。
追加の鍵1:“やらないこと”を決める捨てる戦略
多忙な社会人の合格には、取捨選択が不可欠です。以下はメリハリのための現実的な基準です。
- やる(優先):手続・不服・救済の条文本体、処分性・原告適格・訴えの利益、裁量統制、国家賠償の枠組み
- 短期で圧縮:行政法総論の抽象論(用語定義は押さえ、細部の学説対立は深入りしない)
- 後回し/直前期補充:地方自治法の細部(基本構造は押さえ、細かな数値や手続の枝葉は直前チェックで対応)
合格最短の思想:高頻度×配点大×定着しやすいものからやる。全科目満点主義は不合格の近道です。
追加の鍵2:記述式(配点40点)を“60〜120字テンプレ”で攻略
行政法は記述式の主戦場にもなり得ます。条文知識+判例枠組みを短文テンプレに落としておくと、本番の思考時間を節約できます。
60〜120字テンプレ(例)
- 処分性の判断
「処分性は、当該行為が公権力の主体による一方的行為で、直接国民の権利義務または法律上の地位に具体的影響を及ぼすかで判断する。」 - 原告適格
「原告適格は、当該法規が保護する個別的利益の帰属を基準とし、当該行為により法律上保護された利益を侵害されるおそれがある者に認められる。」 - 裁量権の逸脱・濫用
「裁量の適否は、目的との合理的関連性、判断過程の合理性、平等・比例原則等に照らし、社会通念上著しく妥当性を欠く場合に違法となる。」
運用法:テンプレは書き写す→声に出す→過去問の事案に当てはめる。“型→事案”の順で訓練すると、本番の筆が止まりません。
行政法記述の「型」を論点別にまとめた記事も用意しています(直前期はこれだけ回せばOK)。
追加の鍵3:40代でも回る“90分×毎日”の設計
1日の型(合計90分)
- 朝(20〜30分):短尺講義1本+条文素読
- 昼(15〜20分):一問一答+AIまたは暗記アプリで弱点潰し
- 夜(40〜50分):過去問1セット(行政法)→解説メモ→60字記述1問
ゼロの日を作らない。 5〜10分でも条文か一問一答だけは触れる。連続学習の断絶こそ最大の敵です。
体験談・感想
- 43歳・メーカー勤務(初学)
「条文→短問→過去問→条文に戻るの往復で“根拠を言う癖”がつき、2周目で正答率が65%に。3周目は80%超で安定しました。」 - 47歳・時短勤務(再挑戦)
「判例は“基準→当てはめ”をA4一枚に縮約。言い換え問題への抵抗感が消え、記述でも文章の骨格が崩れなくなりました。」 - 51歳・自営業(短期集中)
「地方自治の細部は直前週に回す“割り切り”で、救済法に時間を集中。択一の取りこぼしが激減しました。」
※体験談は編集部ヒアリングをもとに匿名化・要約しています。
よくある落とし穴と回避策
- 落とし穴:「講義を聞いて満足」
回避:当日中に短問→過去問まで一往復(入力→出力→修正) - 落とし穴:判例本文の丸暗記
回避:要旨→基準→結論→当てはめの4点整理+言い換え練習 - 落とし穴:地方自治の細部に時間を吸われる
回避:基本構造だけ先に固め、細部は直前チェックリスト化
直前60日プラン(行政法特化)
- Week1–2:救済・不服の条文総点検(穴埋めチェック)
- Week3–4:過去問(直近3年)を本番時間で×2周
- Week5:模試・記述の総仕上げ(60字テンプレ全回転)
- Week6–7:取りこぼし論点の横断(処分性・原告適格・裁量統制)
- Week8(試験週):条文番号・期間・手続主体の数字系だけ一気に再固定
行政法学習チェックリスト(保存して使える)
- 手続・不服・救済の条文“趣旨”を1行で言える
- 処分性・原告適格・訴えの利益を例で説明できる
- 裁量統制の審査密度を基準語で言語化できる
- 国家賠償の要件を自分の言葉で言える
- 過去問(直近5年)3周/正答率**80%**を確認
- 60〜120字テンプレを毎日1問書いている
- 地方自治の細部は直前チェックに回す計画がある
まとめ:行政法は“最重要×最効率”の得点源。合格率を上げるのは、優先順位と反復です。
- 条文理解を徹底(手続・不服・救済が主柱)
- 判例は頻出パターンに絞って言い換え耐性を付ける
- 過去問で型を体得(直近5年×3周)
- 捨てる戦略と記述テンプレで短時間でも合格点へ
今日からやるべきことはシンプルです。
① 条文(趣旨)を1行で言えるか確認 → ② 短問演習 → ③ 過去問1セット。
これを毎日90分、連続で積む。合格は積み上げの先にあります。
忙しい社会人に人気の通信講座
- アガルート行政書士講座
添削/質問/合格特典が手厚い。一発合格を狙う人に。
- 資格スクエア 行政書士講座
AIの復習最適化(脳科学ラーニング)×わかりやすい講義で、短時間でも理解が定着しやすい設計。価格と品質のバランスを重視する人に。
- フォーサイト行政書士講座
フルカラー教材+音声講義+eラーニングで理解が進む。通勤学習を習慣化したい人に。
- スタディング行政書士講座
スマホ完結/短い講義/AI復習でスキマ学習に強い。価格を抑えたい人に。
※講座選びは「時間の使い方に合うか」で判断を。無料体験やサンプル講義で確認してから決めると失敗しません。
付録:行政法・60〜120字テンプレの作り方(自習用)
- 条文の趣旨を20〜30字で要約
- 判断枠組みを40〜60字で固定
- 事案への当てはめを20〜30字で添える
→ 合計80〜120字で骨格が崩れない答案が完成。毎日1問、声に出してから書くのがコツです。
最後に
行政法は、正しく絞り、正しく回すだけで合格点に直結します。年齢は関係ありません。今日の90分を積み上げるかどうか。ここから、合格の曲線が変わります。一歩目は、条文の“趣旨を1行で言う”ことから。
行政法を得点源にしたら、次は「全体設計」と「実戦での使い方」を確認しましょう。あわせて読むなら、次の3本です。

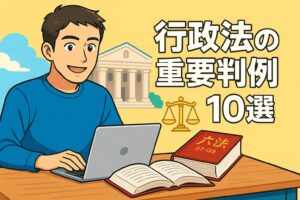


コメント