目次
はじめに
「今日も机に向かえなかった…」
仕事・家事・子どもの寝かしつけ。40代になると、気合と根性だけでは続きません。大事なのは“長時間やる”ではなく、“毎日まわせる設計”です。
本記事は、夜は20分だけ、残りは通勤や家事のスキマで稼ぐやり方に統一。さらに宅建業法に先に全振りして、短期間で合格点に乗せるスケジュールを具体化しました。読み終えたら、そのまま真似できます。
合格に必要な勉強時間(現実的な目安)
- 初学者:300〜400時間
- 法律に触れたことがある人:250〜300時間
- 行政書士・司法書士の学習経験あり:150〜200時間
重要:この時間を夜だけで作らないこと。
夜は最大20分、残りは耳学習と一問一答で積み上げます。
あわせて読みたい


宅建試験の合格率推移と合格ラインの仕組み【2025年最新版・社会人向け】
「毎年20万人以上が受けるのに、合格率は低い……自分もいける?」「合格ラインが変わるって聞くけど、何点を目指せば安全?」 結論:合格ラインは相対評価で毎年動きます…
最短合格の基本戦略(これだけ守ればOK)
- 宅建業法に先に全振り(最初の4〜8週間)
→ 配点40%。ここで9割(18/20)狙いを先に作る。 - ノートは作らない
→ 過去問集の余白に“正誤の決め手を1行メモ”で集約。 - 夜20分固定+スキマ時間で稼ぐ
→ 続く設計にする。根性より回転数。 - 直前期は“新しい知識”を捨てる
→ 使う教材に載っていない情報は切る。点になる所だけ磨く。
あわせて読みたい

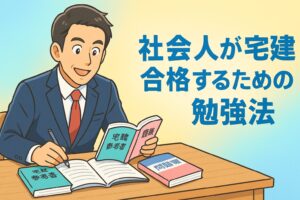
社会人が宅建合格するための勉強法【40代からでも遅くない・低エネルギー設計版】
はじめに 仕事が終わるころにはクタクタ。家に帰ればご飯・お風呂・片付け。「今日も机に向かえなかった…」――そんな日が続くと、宅建の本を開くのが怖くなります。 でも…
6か月モデルの“逆算スケジュール”(社会人用に再設計)
フェーズ0(全期間共通の1日の回し方)
- 朝・通勤:音声講義 or 一問一答アプリ(15〜40分)
- 昼休み:×肢だけ高速で5〜10問(10〜15分)
- 夜:20分だけ「宅建業法/法令:数字」「民法:人物関係の図+決め手1行」
※清書・まとめ禁止。過去問の余白に書くだけ。
フェーズ1:1〜2か月目(宅建業法 全振り)
- 目標:過去問 年度別3年分×3周(業法のみ)
- 夜20分タスク:
①設問の人物・要素を書き出す → ②正誤の決め手を1行 → ③同テーマを3問連打 - 休日は誤答テーマの“肢だけ”復習(本文は見ない)
フェーズ2:3〜4か月目(法令上の制限 → 民法の順)
- 法令:数字と用途は表で丸暗記(建ぺい・容積・用途地域・開発許可)
→ アプリで数字カードを反復 - 民法:人物関係を図にして当てはめ練習
→ 契約解除/意思表示/賃貸借/相続/時効を優先
フェーズ3:5か月目(模試で時間配分を固める)
- 本試験2時間の順番を固定:業法 → 法令 → 権利 → 税その他
- 模試は回数より復習密度:「なぜ×か」を1行メモで過去問に戻す
フェーズ4:6か月目(直前総仕上げ)
- 新しい教材は開かない
- 業法は誤答テーマの肢だけ一気に回転
- 法令の数字/税・統計は数値だけ最終確認
- 民法は図→結論の骨子だけ磨く(清書はしない)
科目別“やることを絞る”チェックリスト
宅建業法(最優先)
- 重点:35条・37条、報酬額、8種制限、営業保証金/保証協会
- 行動:過去問に決め手1行、同テーマ3問連打
- 目標:18/20 正答
法令上の制限
- 重点:建ぺい率/容積率、用途地域、開発許可、農地
- 行動:数字カード化→ アプリ反復(清書不要)
- 目標:6/8 正答
権利関係(民法)
- 重点:意思表示、解除/取消、賃貸借、相続、時効
- 行動:図(誰が誰に何を請求)→ 決め手1行
- 目標:8/14 正答(深追いしない)
税・その他
- 重点:よく出る税/統計
- 行動:直前に数値だけ確認
- 目標:4/8 正答
体験談
- 42歳・営業
「夜は20分だけ。“図+決め手1行”に変えたら業法が9割安定。直前は肢だけを回して本番36点で合格。」 - 39歳・事務
「ノート作りで燃え尽き→過去問の余白1行メモに切替。法令の数字はアプリで暗唱、労力が半分に。」
よくある落とし穴と回避策
- まとめノート作り → 時間のムダ。過去問の余白に1行へ統一
- 民法を深追い → 図の骨子で止める。難問は捨てる
- 新しい教材に浮気 → 直前期は今の教材にない知識は捨てる

私もノートづくりに時間をかけ過ぎて失敗した経験があります。
皆さんはこのような失敗をしないようにしてください。
模試の使い方(1回で価値を最大化)
- 2時間通しで解く → 順番を固定する(業法→法令→民法→税)
- 復習は×の原因を、1行で過去問の解説に記載し、説明できるようにする。
- 新規知識は拾わない(頻出分野だけを確実に得点できるようにする)
まず何を買えばいい?(最小構成)
- 基本書:図が多い“1冊完結型”(見やすいものを)
- 過去問:年度別+分野別の両方があると直前に便利
- アプリ:一問一答 & 数字カードを反復できるもの
参考:
『みんなが欲しかった!宅建士の教科書』/『過去問宅建士(TAC出版)』/各社の直前模試



ただし、短期間で効率よく合格したい方には、通信講座の利用をおすすめします。
おすすめ通信講座
- アガルート(宅建):過去問の論点を「テーマ別→答練→直前総まとめ」の流れで回せる設計。直前予想・模試と質問対応(プランによる)で“詰まり”を解消しやすい。
- 資格スクエア(宅建):スマホで区間リピート・検索性◎。スキマ反復がしやすい
- スタディング(宅建):倍速・音声ダウンロードが強い。耳学習メインの人に
- フォーサイト(宅建):フルカラー図解で理解の初速が上がる。初学者の最初の1冊代わりに
どれも「高い=必ず合格」ではありません。“あなたが毎日学習サイクルを回せる機能”かどうかで選ぶのがコスパ最強。
あわせて読みたい

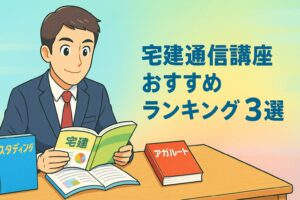
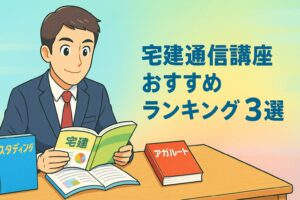
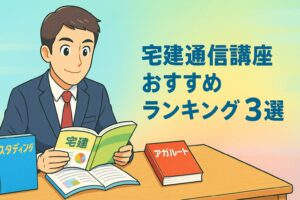
【徹底比較】宅建通信講座おすすめランキング3選【コスパ重視・体験談付き|2025年版】
「短期間で結果を出したい/ムダなく合格したい」——そんな30代・40代の社会人にとって、宅建の通信講座は価格だけでなく、時短性・再現性(合格しやすさ)・継続しやす…
よくある質問(FAQ)
Q. 平日に勉強時間を作れません。
A. 夜20分固定+通勤・家事の耳学習でOK。20分で図と1行メモだけ終えるタスクにしましょう。
Q. 半年で受かりますか?
A. 業法に先に全振りできれば現実的。業法18/20の土台ができると合格点が近づきます。
Q. ノートを作らないのが不安です。
A. 直前に見るのは過去問集です。そこに決め手1行が集約されている状態が最強です。
関連記事
あわせて読みたい




宅建とは?難易度・合格率・試験内容を徹底解説【初心者向け・社会人OK版】
「資格を取りたいけれど、何から始めればいいのか分からない」「宅建ってよく聞くけど、どんな試験?難しい?」 結論:宅建は初心者でも合格できます。ポイントは、配点…
あわせて読みたい

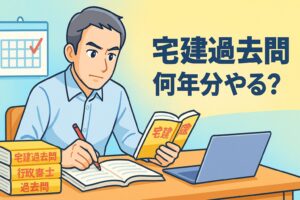
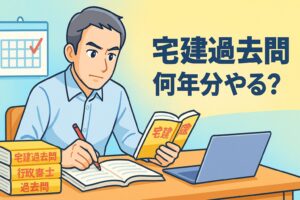
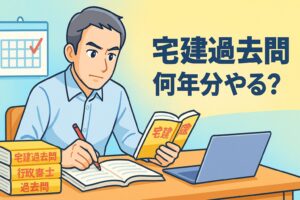
宅建過去問は何年分やるべき?効率的な解き方と活用法【社会人向け・保存版】
「宅建試験に向けて過去問を解き始めたけれど、何年分やれば十分なのだろう?」仕事や家庭と両立している30代・40代の方から、最も多く寄せられる質問です。時間は限ら…
あわせて読みたい

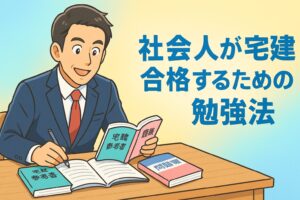
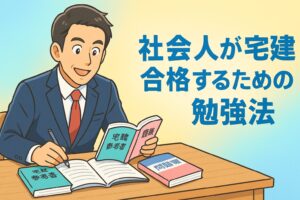
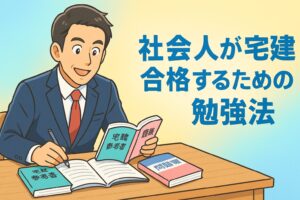
社会人が宅建合格するための勉強法【40代からでも遅くない・低エネルギー設計版】
はじめに 仕事が終わるころにはクタクタ。家に帰ればご飯・お風呂・片付け。「今日も机に向かえなかった…」――そんな日が続くと、宅建の本を開くのが怖くなります。 でも…
まとめ(今日の一手)
- 必要時間は300〜400h。ただし夜20分固定でOK。
- 最初の4〜8週間は宅建業法に全振り(9割狙い)。
- ノート禁止。過去問の余白に決め手1行。
- 直前は新知識を捨てて、肢の反復で仕上げ。
👉 今すぐやること:宅建業法の過去問を年度で1年分解く。各×問題に“正誤の決め手を1行”だけ書き込みましょう。
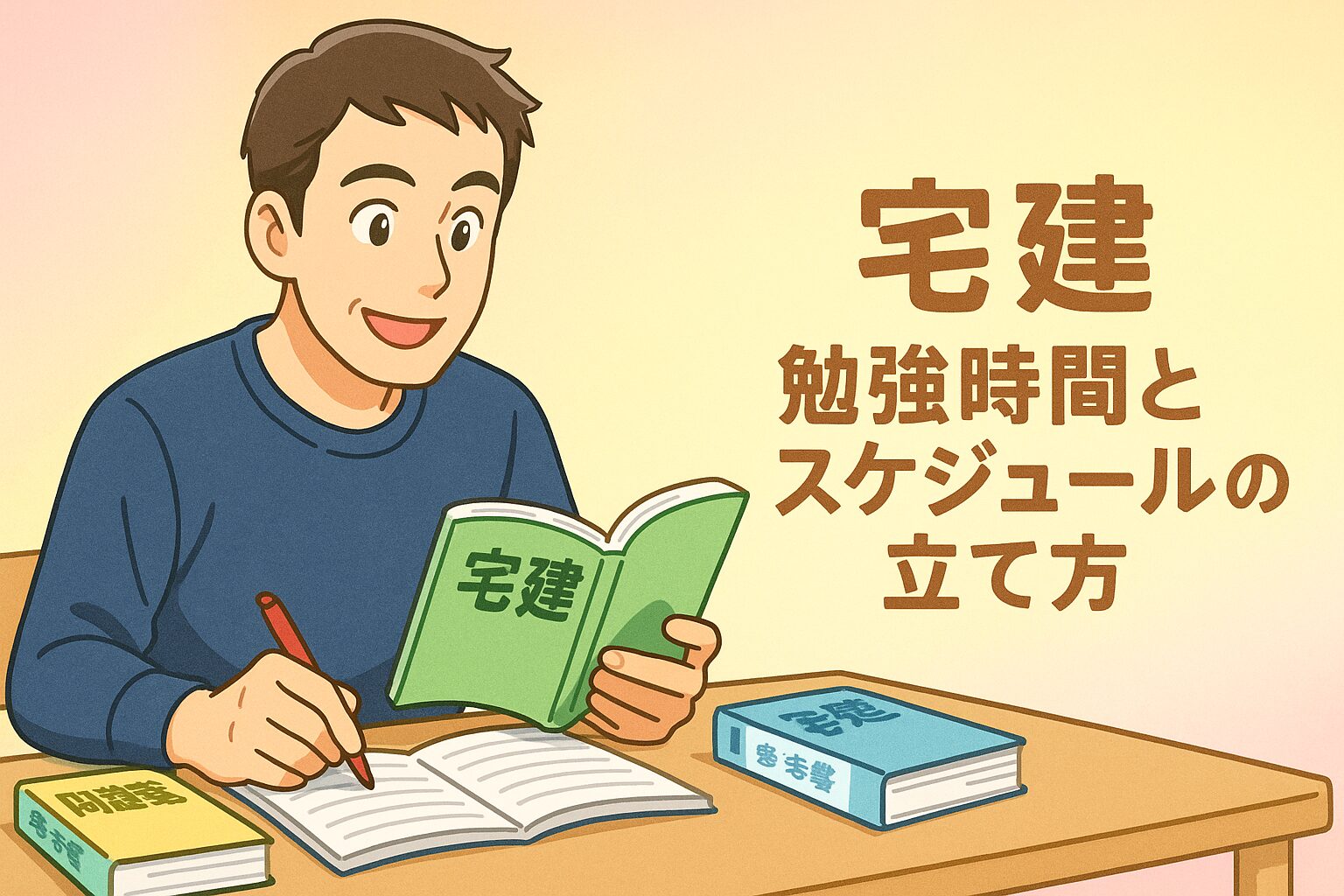
コメント