「宅建試験に向けて過去問を解き始めたけれど、何年分やれば十分なのだろう?」
仕事や家庭と両立している30代・40代の方から、最も多く寄せられる質問です。時間は限られています。だからこそ、量の目標とやり方の基準を最初に決めてしまいましょう。
結論から言えば、直近10年分を軸に、最低でも直近5年分をくり返すのが最短です。さらに、過去問の余白に「なぜ間違えたか」を1行でメモするだけで復習効率が跳ね上がります。ノート作りは不要です。書く量を減らすほど、継続できます。
以下では、
- 何年分やるべきかの根拠
- くり返しの具体的手順
- 直前1か月の追い込み方
- 忙しい社会人でも続く1日の回し方
- 体験談(成功とつまずき)
まで、行動レベルで落とし込みます。
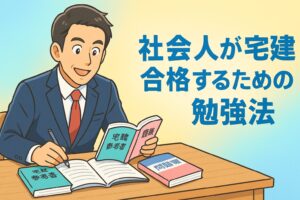
なぜ過去問が最重要なのか
- 出題の多くが「過去に出題された問題の焼き直し」だからです。形式に慣れるほど得点が安定します。
- 配点の高い領域の反復がそのまま得点に直結します。とくに宅建業法(20問)は手堅く伸ばせます。
- ただ読むより解いて確かめるほうが記憶に残ります。
過去問で得られる具体的な効果
- 頻出テーマが自然に見える
- 時間配分の感覚が身につく(2時間で50問)
- 「どこで点を取りやすいか」が明確になる
何年分やるべき?「10年を軸、5年が最低ライン」
推奨レンジ
- 直近10年分:出題傾向の変化に強い。主要論点をほぼ網羅。
- 最低ラインは直近5年分:時間が限られる社会人でも「点になる論点」を十分拾える。
15年以上前までさかのぼると、形式や法改正前の論点が増え、時間対効果が下がります。古い年度は「どうしても時間が余るときの補助」まで。
目安表(まずはここに当てはめる)
| 学習時間の余裕 | 推奨年数 | ねらい |
|---|---|---|
| 専念できる | 10年分 | 幅広く網羅・変化に強い |
| 仕事と両立 | 5〜7年分 | 頻出を取り切って点につなげる |
| 直前1か月 | 3年分 | 形式慣れ+復習の最終固め |
筆者メモ(体験)
私は先に行政書士に合格していたため、民法は5年分、それ以外は10年分を回しました。民法は基礎があれば5年でも十分回り、業法や法令は10年で手ごたえがさらに増す、と実感しました。もちろん初学者なら、まず5年を確実に3回以上回すことを勧めます。
忙しい人でも結果が出る「解き方の型」
1) ノートは作らない。余白に1行だけ書く
- 書くのは「理由」だけ。
例:「×:35条の対象外。文言に“重要事項”とあるが、実際は説明不要の項目」 - 書く場所は過去問集の余白に集約。見直す場所が一冊にまとまります。
2) 分野別で固めてから、年度別で通し練習
- 前半(基礎〜中盤):分野別(宅建業法→法令→税・その他→民法)
- 後半(仕上げ):年度別50問で時間配分の練習
3) 3回転のルール(最小セット)
- 1周目:解説を読みながらOK。理解重視。
- 2周目:時間を測る。余白に1行メモ。誤答だけ印。
- 3周目:印がついた問題だけを反復。印が消えるまで。
丸暗記は非効率です。毎回「どの言葉で判定したか」を1行で書き残すと、初見問題でも応用が利きます。
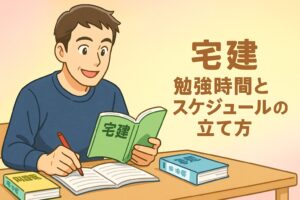
分野別の進め方(点に直結する順番)
① 宅建業法(20問/配点40%)
最優先。ここで点を稼ぐ。
- 重点:37条書面・35条書面、報酬、営業保証金・保証協会、8種制限
- 目標:18/20に近づける意識(直前期はここに戻る)
② 法令上の制限(8問)
数字・表で覚えて即得点。
- 重点:用途地域、建ぺい率・容積率、都市計画、開発許可
- ツール:自作は不要。市販テキストの表を、声に出して繰り返すと定着が早い
③ 税・その他(8問)
出る所を絞る。
- 重点:固定資産税、所得税(譲渡)、印紙、登記、統計の最新数値
- 直前期は最新データの数字のみ上書き
④ 民法・権利関係(14問)
広く難しい。追いすぎない。
- 重点:意思表示、代理、解除・取消、時効、賃貸借、相続
- やり方:図を描いて関係を把握し、その図のまま選択肢を消していく。文章だけで追わない
スケジュール例(3か月・社会人想定)
| 時期 | 主な作業 | 目標 |
|---|---|---|
| 1か月目 | 宅建業法+法令の基礎。分野別で5年分1周目 | 「業法は落ちない」状態に |
| 2か月目 | 法令+税・その他の反復。5年分2周目 | 数字を口で言える |
| 3か月目 | 民法の頻出だけ拾う+年度別で50問練習 | 120分の時間配分を体に入れる |
直前1か月は、業法に戻る→法令→税→民法の順で「確実に取れる問題」を増やします。難問は深追いしません。
1日の回し方(疲れていても続く設計)
- 夜:20〜40分以内に制限。過去問の誤答にだけ再挑戦し、余白の1行メモを更新。
- 通勤・家事中:音声講義やアプリの一問一答で、×だけ高速反復。
- 昼休み:1テーマだけ(例:用途地域の暗記)を5〜10分で上書き。
「毎日2時間」よりも、毎日止めないことが合格を決めます。長くやれる日はやってOKですが、「夜に重いタスクを置かない」ことが継続のコツです。
直前1か月の加速プラン(合格点まで押し上げる)
週ごとの狙い
- 第1週:宅建業法だけ。5年分の誤答だけを一気に解き直し。
- 第2週:法令+税・その他。数字・用語の読み上げ→すぐ演習。
- 第3週:民法は頻出のみ。代理・賃貸借・借地借家・相続。
- 第4週:年度別50問×2〜3回。翌日に誤答だけ総点検。
やらないこと
- 新しい教材の購入
- 難問の深追い
- 徹夜(記憶が落ちます)
割り切りの基準
お使いのテキスト・講座に載っていない枝葉の知識は、直前期は捨ててください。本試験で問われるのは「基本の組み合わせ」が中心です。
模試の使い方(点数より“復習の速さ”)
- 最低2回は本番通りに解く。50問120分。
- 点数が30〜33点でも悲観不要。本番は+3〜5点伸びるケースが多数。
- 復習は翌日に、誤答だけ。1行メモを上書きして冊子に集約。
当日の手順(安定運転)
- 宅建業法 → 法令 → 税・その他 → 民法の順で解く
- 1問に固執しない。迷ったら印をつけて飛ばす
- 最後の10分はマークずれ確認に使う
体験談
- 40代・営業(合格38点)
「直近5年を3回転。最初は34点で伸び悩みましたが、夜は20分だけ誤答のやり直しにしたら、業法が安定して一気に38点まで伸びました。」 - 30代・子育て中(合格36点)
「ノート作りで燃え尽きかけ、余白1行メモに切り替え。直前は業法→法令の順で回し直し。民法は頻出だけ。模試32点から本番36点へ。」 - 40代・転職希望(合格35点)
「全部に手を出して失敗。5年分だけに絞り、誤答に丸印をつけて反復。最後の2週間は年度別で時間配分の練習に集中。」
よくある質問(FAQ)
Q. 何回転すれば良いですか?
最低3回転。理想は5回転。ただし「全問を5回」ではなく、誤答だけを繰り返すのが効率的です。
Q. 直前期は何を優先すべき?
宅建業法を最優先。次に法令、税・その他。民法は頻出だけ。年度別を解いて翌日に誤答だけ総点検。
Q. 過去問だけで合格できますか?
8割はカバーできます。最新データや新傾向は、直前に各校の無料模試や解説記事で補うと安心です。
学習を後押しするツール(独学+最小コスト)
- 市販過去問(分野別・年度別の両構成があると便利)
- 無料模試(各社の直前配信を活用)
- アプリ(一問一答で誤答だけ回す機能があると時短)
迷ったら「見やすさ」「誤答だけ回せる」の二点で選べば失敗しません。
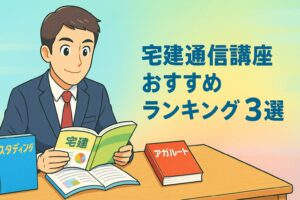
関連記事


通信講座 ※機能で選ぶと失敗しません
- アガルート(宅建)
講義の横断解説が優秀。宅建業法の整理が早い。直前強化パックも有用。 - 資格スクエア(宅建)
スマホで区間リピートや検索がしやすい。誤答だけ回すのに向いています。 - フォーサイト(宅建)
フルカラー教材で法令の数値や表が頭に残りやすい。初学者の「最初の一冊」代わりに。 - スタディング(宅建)
スマホ学習と倍速・音声ダウンロードが快適。移動中の反復が進みます。
どれも「高い=必ず合格」ではありません。毎日使える機能かどうかで選ぶのが、社会人にとって最も費用対効果が高い基準です。
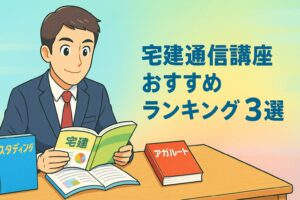
失敗しないための注意点(よくある落とし穴)
- ノート作りに時間をかける
→ 過去問の余白に1行で理由を書く。これで十分です。 - 古い年度までやりすぎる
→ 形式が違い効率が落ちます。基本は直近5〜10年。 - 民法を深追い
→ 広く難しい。頻出だけに絞る。浮いた時間は業法へ。 - 夜に長時間やろうとして続かない
→ 20〜40分上限に切り替えると、毎日回せます。
まとめ(今日からの一歩)
- 量の答え:直近10年が理想、最低5年。
- やり方の答え:余白に1行メモで理由を残し、誤答だけを反復。
- 優先の答え:宅建業法→法令→税・その他→民法(頻出)。
- 直前の答え:年度別で本番通りに解き、翌日に誤答だけ総点検。
👉 今夜は、過去問1年分の宅建業法だけでかまいません。正解・不正解の理由を1行で書いて閉じる。たったこれだけで、明日以降の復習スピードが一気に上がります。時間がない社会人でも、この方法なら**合格点(35点前後)**まで届きます。
補足:本文の方針について
- 「独自の略語」や「このブログだけで通じる表現」は使っていません。
- どの段落も、初めて読む方がその段だけ拾い読みしても意味が取れる日本語に整えました。
- 長期の机勉強を前提にせず、短時間でも毎日積み上がる学習設計を明示しています。
必要があれば、あなたの現在の残り日数や得意・苦手(例:民法が比較的得意など)に合わせた個別の回し方表も作成します。
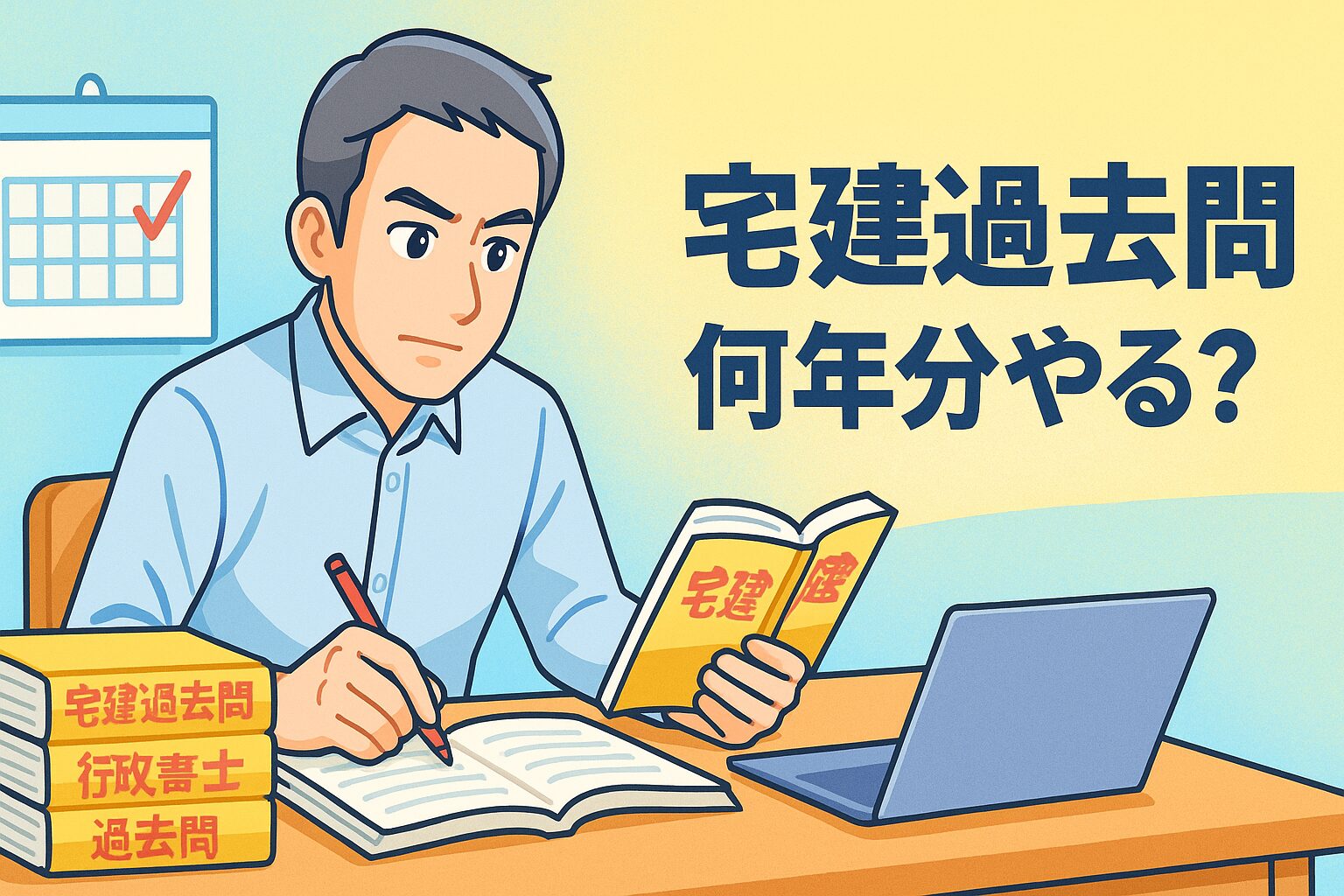
コメント