「どれを買えばいい?」よりも大事なのは、“どう使えば夜20分でも学習が進むか”です。
結論:テキストは1冊固定/過去問は余白に1行メモで集約/宅建業法を最初の2か月で潰す。
目次
学習時間と教材の役割(まずは前提)
- 必要学習時間:300〜400時間(初学者の目安)
- 役割分担:基本書で理解 → 過去問で定着 → 模試で時間配分を調整
- 社会人は夜20分の机学習+スキマ学習(音声・一問一答)が最短です
あわせて読みたい


宅建の独学は本当に可能?メリット・デメリットと“低エネルギー設計”の勉強法
「独学で受かる?」「お金は抑えたいけど、時間もない…」結論:独学で十分合格は可能です。ポイントは、配点の高い科目に集中し、疲れていても毎日まわせる仕組みにする…
総合テキスト ランキング【2025】
評価軸は「図・色分け」「スマホ相性」「音声の有無」「過去問連動」「法改正の速さ」。
迷ったら第1位でOK(そこから動かないのが勝ち)。
第1位:みんなが欲しかった!宅建士の教科書(TAC出版)
- 強み:フルカラー/図が多い/見出しが整理され“読み疲れ”しにくい
- スキマ適性:章扉の要点つまみ食い→音声読み上げ機能の自作もしやすい
- 連動:同シリーズの過去問と往復がスムーズ
- 向く人:初学者全般・民法が不安な人
第2位:合格のトリセツ 基本テキスト(LEC)
- 強み:会話形式+図解で引っかかりを解消/要点が短く頭に入りやすい
- スキマ適性:節ごとの“1ページ要約”で朝の5分復習が楽
- 連動:「出る順」問題集(後述)と相性良し
- 向く人:活字が苦手な人/短時間で概要を掴みたい人
第3位:スッキリわかる宅建士(TAC出版)
- 強み:講義調で理解の流れが自然/イラスト多め
- スキマ適性:章末“要点チェック”→耳学習に落とし込みやすい
- 連動:シリーズ問題集で反復しやすい
- 向く人:短時間の細切れ読みを繰り返したい人
第4位:らくらく宅建塾(住宅新報出版)
- 強み:語呂合わせ・ユーモアで記憶に残る
- スキマ適性:語呂のカード化が楽
- 向く人:固い文章が苦手/楽しさ重視
第5位:パーフェクト宅建(住宅新報出版)
- 強み:網羅性と精度/法改正反映が早い
- スキマ適性:辞書的利用向き(読み切ろうとしない)
- 向く人:再受験・深掘りが必要な人
問題集・過去問 ランキング【2025】
まずは過去問。分厚くてもノート作りはしない。
余白に「正誤の決め手」を1行、これで直前期の伸びが変わります。
第1位:過去問宅建士(TAC出版)
- 強み:出題傾向の切り分けが上手い/年度別×分野別の両構成あり
- 使い方(低エネ)
- 1周目:解説を読みつつ○×だけ
- 2周目:間違えた理由を余白に1行(条文番号やキーワード)
- 3周目:×肢だけ高速回し
- 最優先:迷ったらこれ
第2位:出る順宅建士 合格問題集(LEC)
- 強み:頻出度順で効率学習/短期合格設計
- 使い方:宅建業法パートを最初の2か月で回し切る→“9割確保”の基盤に
第3位:わかって合格る宅建士 過去問題集(日建学院)
- 強み:「わかる→解ける」導線が明確/図解多め
- 使い方:つまずきやすい民法の“橋渡し”に最適
第4位:スッキリわかる 宅建士 過去問(TAC出版)
- 強み:テキスト連動で復習が迷子にならない
- 使い方:移動中の1問単位回しに
第5位:直前予想模試(LEC/TACなど)
- 強み:本番90~120分の緊張感と時間配分をリハーサル
- 使い方:回数<復習密度。×の根拠を1行だけ追記
分野別「先に点を取りにいく」教材の使い分け
- 宅建業法(20問=40%):最初の2か月は全振り
- 薄めの分野別問題集→同じ論点を短い周期で何度も回す
- 目標:18/20(9割)
- 法令上の制限(8問):
- 数値×用途の表を作らず、既存の表をカード化(アプリでもOK)
- 権利関係(14問):
- 人物関係の図→消去法。夜は20分で図+決め手メモだけ
低エネルギー設計:教材の“回し方”テンプレ
- 夜(最大20分):
- 過去問の図+正誤の決め手を1行(清書・ノートは禁止)
- スキマ(40〜80分):
- テキスト目次を音読・音声化(1.5〜2倍速)
- 一問一答アプリで×肢だけ反復
- 週末(60〜120分):
- 業法の弱点分野をまとめて叩く
- 模試は週1まで(復習密度優先)
体験談
- 41歳・経理
「3冊買って迷子→みんほし1冊に固定。過去問余白1行メモで直前の復習が圧縮。本番36点で一発合格。」 - 38歳・営業
「出る順の業法だけ先に3周。朝は1章5分の耳学習、夜は20分で図+決め手。業法9割安定で他が多少崩れても安全圏に。」
よくある質問(FAQ)
Q. テキストは何冊持つべき?
A. 1冊固定。足りない部分は過去問の解説で補うのが最短です。
Q. ノートは必要?
A. 不要です。過去問の余白に1行(条文番号・キーワード)で十分。清書は時間の無駄。
Q. 模試は何回?
A. 1〜2回でOK。回数より復習密度。×の理由を1行追記。
関連記事
あわせて読みたい

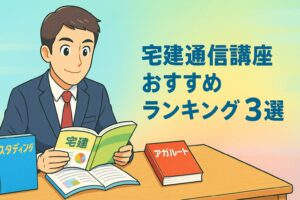
【徹底比較】宅建通信講座おすすめランキング3選【コスパ重視・体験談付き|2025年版】
「短期間で結果を出したい/ムダなく合格したい」——そんな30代・40代の社会人にとって、宅建の通信講座は価格だけでなく、時短性・再現性(合格しやすさ)・継続しやす…
あわせて読みたい

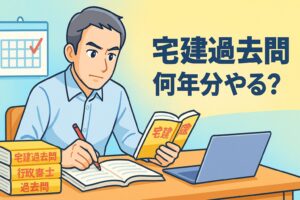
宅建過去問は何年分やるべき?効率的な解き方と活用法【社会人向け・保存版】
「宅建試験に向けて過去問を解き始めたけれど、何年分やれば十分なのだろう?」仕事や家庭と両立している30代・40代の方から、最も多く寄せられる質問です。時間は限ら…
あわせて読みたい


宅建試験の合格率推移と合格ラインの仕組み【2025年最新版・社会人向け】
「毎年20万人以上が受けるのに、合格率は低い……自分もいける?」「合格ラインが変わるって聞くけど、何点を目指せば安全?」 結論:合格ラインは相対評価で毎年動きます…
あわせて読みたい

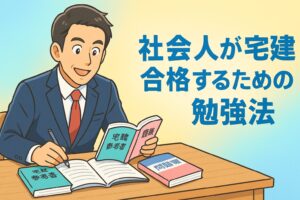
社会人が宅建合格するための勉強法【40代からでも遅くない・低エネルギー設計版】
はじめに 仕事が終わるころにはクタクタ。家に帰ればご飯・お風呂・片付け。「今日も机に向かえなかった…」――そんな日が続くと、宅建の本を開くのが怖くなります。 でも…
おすすめ通信講座
- アガルート(宅建):過去問の論点を「テーマ別→答練→直前総まとめ」の流れで回せる設計。直前予想・模試と質問対応(プランによる)で“詰まり”を解消しやすい。
- 資格スクエア(宅建):スマホで区間リピート・検索性◎。スキマ反復がしやすい
- スタディング(宅建):倍速・音声ダウンロードが強い。耳学習メインの人に
- フォーサイト(宅建):フルカラー図解で理解の初速が上がる。初学者の最初の1冊代わりに
どれも「高い=必ず合格」ではありません。“あなたが毎日学習サイクルを回せる機能”かどうかで選ぶのがコスパ最強。
あわせて読みたい

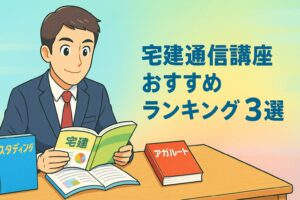
【徹底比較】宅建通信講座おすすめランキング3選【コスパ重視・体験談付き|2025年版】
「短期間で結果を出したい/ムダなく合格したい」——そんな30代・40代の社会人にとって、宅建の通信講座は価格だけでなく、時短性・再現性(合格しやすさ)・継続しやす…
まとめ(今日の一歩)
- テキストは1冊に固定(みんほし or トリセツが無難)
- 宅建業法を2か月で9割へ(分野別問題集→過去問)
- 過去問の余白に“正誤の決め手”を1行。ノートは作らない
👉 今すぐ:業法の過去問を1年分解いて、各肢の“決め手”を1行メモ。
これで“勉強ゼロの日”がなくなり、得点が積み上がります。
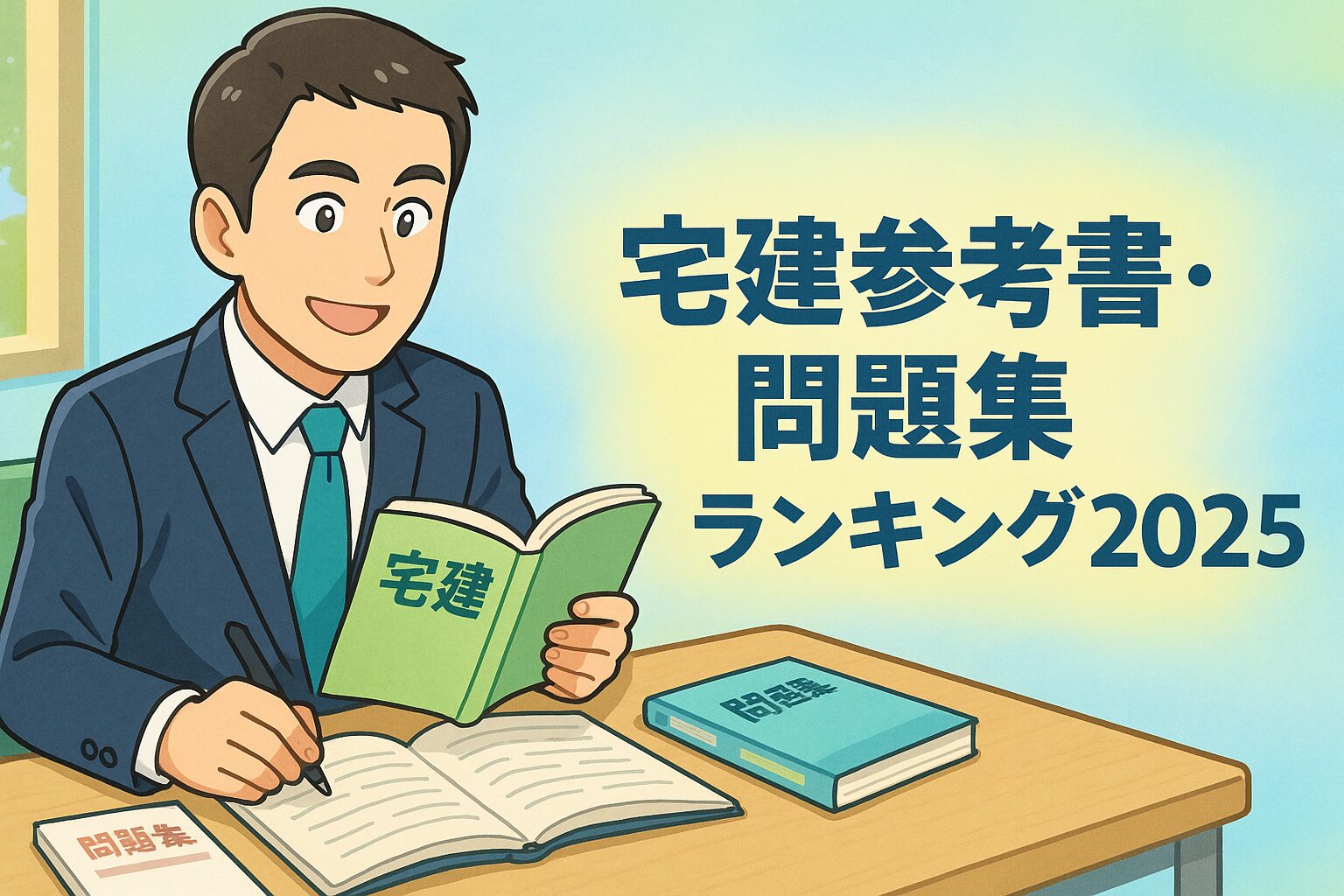
コメント