「40代から宅建に挑戦して、本当に合格できるのだろうか?」——仕事や家庭があると、勉強時間の確保だけでひと苦労。若いときのように一気に覚えられない不安もありますよね。
でも大丈夫。やり方を“現実に合わせて”変えれば、40代からでも十分に合格できます。鍵は、がんばり続ける根性ではなく、毎日続けられる仕組みです。
この記事では、40代の社会人が無理なく合格ラインに届くための具体的な学習法、時間の作り方、科目別の進め方を、実際の体験談も交えてわかりやすく解説します。行政書士などとのダブルライセンスを見据える方にも役立つ内容です。
※この記事では、40代から宅建合格を目指す方向けに
・無理のない勉強スケジュール
・挫折しない学習の組み立て方
・実際に多くの人が選んでいる学習手段
をまとめています。
「自分に合った勉強法を知りたい」という方は、
まずこちらのまとめも参考にしてください。
▶ 40代向け|宅建合格に近づく学習方法・講座まとめ
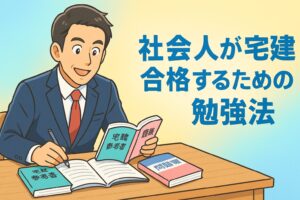
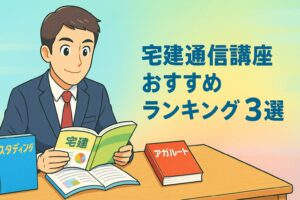
1. 40代でも宅建は十分に合格できる
- 合格率はおおむね15〜17%前後。簡単ではありませんが、社会人の受験者・合格者が多い試験です。
- 40代の強み
- 目的が明確(転職・昇格・副業・独立など)
- 計画を守る力がある
- 実務をイメージしながら学べるため、知識が使える形で残りやすい
ポイント:不安の原因は「時間」と「継続」。ここを仕組みで解決すれば年齢はハンデになりません。
2. 合格までに必要な勉強時間と“毎日の設計”
- 必要学習時間の目安:300〜400時間
- 40代の現実に合う内訳
- 夜の学習は毎日20分までに制限する(疲れていても続く分量に固定)
- 通勤・家事の時間を使って60〜80分を音声や一問一答アプリで積み上げる
夜に長時間の机学習を前提にすると、ほぼ間違いなく続きません。
“夜は20分まで”と決めることで、翌日も同じペースで戻ってこられます。
3. 最短で合格ラインに届く学習の順番
① 宅建業法(20問=全体の40%)を最優先
- 最初の1〜2か月は、宅建業法に集中します。
- 目標:本試験で18/20点前後を狙える安定力。
- やり方:過去問の各選択肢について、誤っている理由や根拠を問題集の余白に1行で書き込む。ノートは作りません。
よく出る範囲:35条・37条(説明書面)、報酬、8種制限、保証協会・営業保証金 など
② 民法(14問):事例は関係図を書いて解く
- 文章だけで追わず、人の関係・時系列・権利の流れを簡単な関係図にする
- 関係図が描けたら、誤っている選択肢から順番に消す(自分の中で順番をあらかじめ決めておく)
- ねらい:読み間違い・思い込みによる失点を減らす
頻出:意思表示、解除・取消、賃貸借、相続、時効
③ 法令上の制限(8問)・税その他(8問)
- 数値や用語は表にして覚える(建ぺい率・容積率・用途地域など)
- 暗記カードやアプリで反復。清書は不要。
- 統計や細かい数字は直前に確認で十分。
4. 1日の進め方(具体例)
- 朝:5〜10分 前日メモの見直し(過去問の余白に書いた1行)
- 通勤:30〜40分 音声講義・一問一答アプリ
- 夜:20分までに制限して、
- 過去問2〜3問
- 間違えた理由を問題集の余白に1行だけメモ
- 週末:45〜60分×2本 本試験形式で時間配分の練習(宅建業法→法令→民法→税・その他の順で、確実に取れる問題から解く)
ノート作りは禁止。書く量が増えるほど続かなくなります。
すべて過去問集の余白に集約し、直前期はその本だけ見返せる状態にしておきます。
5. 直前1か月の調整
- 新しい教材には手を出さない
- 宅建業法の取りこぼしをゼロに近づける
- 民法は関係図+誤答を消す順番で読み違いを防ぐ
- 法令・税は数値・用語の最終確認に絞る
6. 体験談
- 42歳・営業
「夜は子どもを寝かしつけた後の20分だけ。過去問の余白に“誤りの理由”を1行ずつ書く方法に変えたら回転が上がり、宅建業法は安定して9割。本番は36点で合格しました。」 - 39歳・事務
「最初はノート作りで燃え尽きました。問題集に1行だけ書く方式にしてから、直前の見直しが速くなり、法令が+6点伸びました。」 - 45歳・転職希望
「関係図を書いて順番に誤答を消す方法に変えたら、民法の読み違いが激減。合格後、住宅ローン部門に転職できました。」
7. おすすめ教材と使い方(“続けやすさ”基準)
- テキスト:フルカラー・図解多め・1冊で完結しているもの
- 過去問:年度別と分野別の両方があると直前が楽
- 模試:1〜2回で十分。時間配分の練習が目的
使い方の原則
- テキストは迷わず1冊に固定
- 過去問は10年分を回すのが理想(時間が足りなければ、宅建業法を厚めに)
- 復習は余白に1行メモ、直前はその本だけで回せる状態に
8. 通信講座 ※機能ベースで選ぶと失敗しません
ここまで読んで、「自分にもできそう」と感じた方へ。
勉強を続けられるかどうかは、
“やる気”よりも「環境づくり」でほぼ決まります。
特に40代の場合、
・スキマ時間を使いやすい
・復習しやすい
・迷わず続けられる
という条件を満たす教材選びが重要です。
実際に合格者が使っていた教材を、以下にまとめています。
- アガルート(宅建):質疑応答が丁寧。過去問ベースの講義で理解が速い。合格特典あり。
- 資格スクエア(宅建):スマホでの区間リピートと検索が使いやすい。スキマ反復に最適。
- フォーサイト(宅建):フルカラー図解で理解の立ち上がりが速い。初学者の導入に向く。
- スタディング(宅建):倍速・音声ダウンロードが強力。耳学習が中心の人に。
高い講座が必ず合格に直結するわけではありません。
「通勤・家事の合間でも使えるか」「音声とアプリが快適か」で選ぶと、続けやすさが段違いです。
▶ 40代に向いている宅建講座の比較を見る
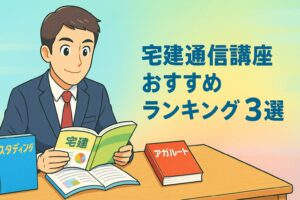
9. よくある質問(FAQ)
Q. 40代からでも本当に合格できますか?
A. 可能です。学習の優先順位(宅建業法→民法→法令・税)と、夜は20分までという制限を守れば、合格ラインに届きます。
Q. 民法が難しくて不安です。
A. 文章で押し切らず、関係図を書いてから選択肢を読み、誤っている選択肢を決まった順番で消す方法にすると、読み違いが減ります。
Q. ノートは作ったほうが良いですか?
A. 原則、作りません。問題集の余白に1行だけ書き込み、直前期はその本だけ見返せる形にします。
10. 行政書士とのダブルライセンスを考えている方へ(関連記事)

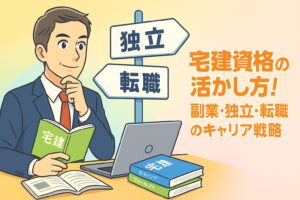


宅建で学んだ民法の基礎は、行政書士でも活かせます。同じ勉強時間を再利用できるのが強みです。
まとめ
- 夜の学習は毎日20分までに制限する(続けるための仕組み)
- 宅建業法を先に完成させ、合格に必要な点を早めに確保する
- 民法は関係図を書いてから、誤っている選択肢を決まった順番で消す
- ノートは作らず、過去問集の余白に1行メモで復習を一元化する
👉 今日の一歩:宅建業法の過去問を1年分だけ。各問題で「誤りの理由」を余白に1行書き込んでください。明日も同じ手順で進めれば、確実に積み上がっていきます。
ここまで読んで、
「自分にもできそう」と感じたなら、それがスタートの合図です。
大切なのは、完璧な準備ではなく
“今日から少しだけ動くこと”。
まずは、
・どんな講座があるのか
・自分の生活に合う学習スタイルはどれか
を知るところから始めてみてください。
▶ 40代向け|宅建通信講座の比較を見る
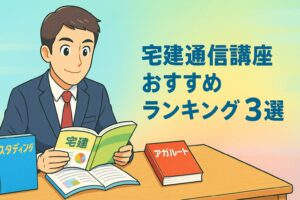
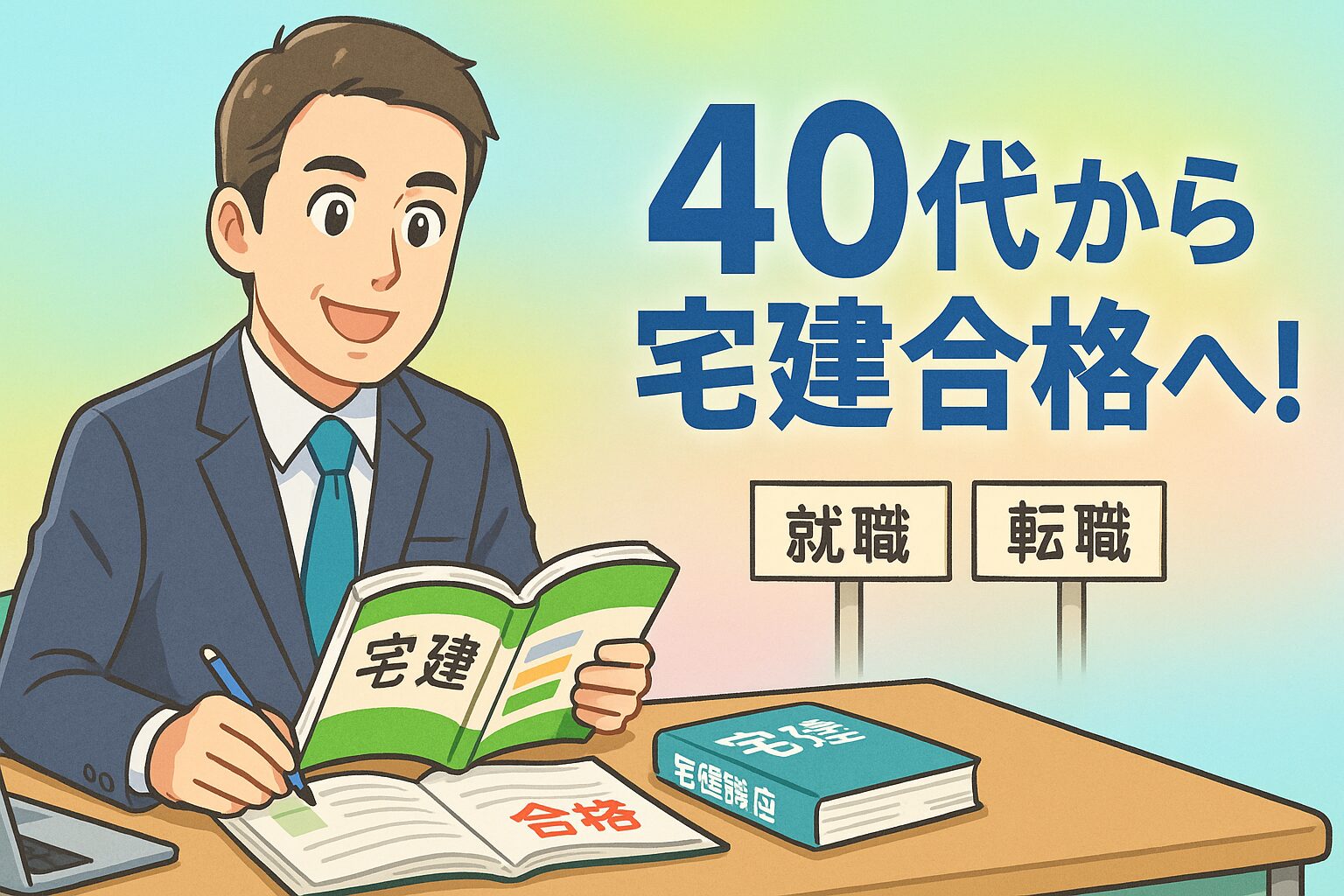
コメント