「択一は何とかなるけど、記述式が怖い…」
30〜40代の社会人から本当によく届く声です。
記述は3問×20点=60点。合格者の平均は24点前後と言われ、まさに合否の分水嶺。
にもかかわらず、多くの受験生が「直前に詰め込む→撃沈」という流れを繰り返しています。
本記事では、最短で記述の合格点(=20〜30点レンジ)に到達するために、
- 何を捨て、どこに集中するか(論点の絞り込み)
- 択一の知識を記述用の言語へ変換する方法
- いつから、どう回すか(開始時期&復習ループ)
を、テンプレとチェックリストで可視化します。
💬 体験談(41歳・営業)
「“択一の正解理由を40〜60字で言語化”し始めた途端、記述が一気に書けるようになりました。書くのではなく“言い換える”感覚です。」
行政書士試験の勉強法を知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

なぜ記述は“少ない練習量”で伸びるのか
- 問われる論点は毎年ほぼ同系統(行政法:処分取消系・不服申立・執行停止/民法:意思表示・債権総論・物権変動など)
- 採点は要件・効果のキーワード命(満点狙いより部分点を積む競技)
つまり「広く深く」ではなく、“狭く深く+型”が勝ち筋。
勉強法1:合格者がやる「答案構成テンプレ」を覚える
■ 40〜60字テンプレ(これだけで書ける)
【設問要求】+【要件(キーワード2〜3個)】+【結論】
- 例:処分取消訴訟
「処分取消の可否は、✱処分性✱原告適格✱出訴期間を満たすかで決まる。本件は○○に該当し適法。」
💬 体験談(35歳・SE)
「“設問要求を冒頭に置く”習慣で、字数オーバーが激減&部分点が安定。」
■ 「事実→条文」へ橋渡しする記述トリガー辞書
| 事実のサイン(問題文) | 連想すべき条文・論点 | 記述キーワード例 |
|---|---|---|
| 「行政庁の通知で不利益」 | 処分性/行政事件訴訟法 | 処分性・法律効果・相手方 |
| 「申請却下/不許可」 | 不服申立・審査請求 | 申立適法・期間・教示 |
| 「執行停止の可否」 | 行訴法25 | 回復困難な損害・緊急性・公益衡量 |
| 「申請から3ヶ月放置」 | 不作為の違法確認訴訟 | 申請権・期間・違法の確認 |
| 「相殺の主張」 | 民法505・506 | 相殺適状・対当額・同種債権 |
| 「錯誤で契約取消」 | 民法95 | 要素の錯誤・重過失・表意者保護 |
| 「第三者が登記取得」 | 物権変動・対抗要件 | 登記対抗・二重譲渡・善意悪意 |
使い方:過去問を解きながら事実のサインにマーカー→条文番号を余白に。
3周目にはサインを見た瞬間、自動でキーワードが出る状態を目指す。
■ 採点者が見る“ミニ採点表”(自分用チェック)
- ① 設問要求が先頭にあるか
- ② 要件が名詞で(処分性・原告適格…)2〜3個並んでいるか
- ③ 結論の主語と述語が噛み合っているか
- ④ 40〜60字に収まっているか(短い=良い)


勉強法2:択一→記述の“逆算学習”で最短化
■ 手順(1問3分の高速ドリル)
- 択一の正解の根拠を条文番号で一言メモ
- その根拠を40〜60字の記述文に“言い換え”
- 模範記述とキーワード突合(抜け1つ=▲5点の感覚で)
💬 体験談(44歳・経理)
「“択一→記述の言い換え”を通勤で毎日3題。2週間で書く恐怖が消えた。」
■ 記述“鉄板10論点”だけを回す(時短リスト)
- 行政法:処分取消/不服申立/執行停止/無効等確認/不作為/原告適格
- 民法:錯誤/相殺/時効完成と援用/解除/対抗要件(登記・引渡)
ここ以外は「読むだけ」OK。“出るところだけ深掘り”が社会人の正解。
■ 72時間リカバリー(模試・演習後の固定ループ)
- 当日:誤答と迷い正解を色分け(迷いが“危険知識”)
- +24h:危険知識を条文→60字で言い換え直し
- +72h:同テーマの別問題で再テスト(書けたら合格)

勉強法3:添削は“回数”より“質”で選ぶ(コスパ重視)
■ 良い添削の条件(ここだけは妥協しない)
- 採点基準(キーワード)を明示してくれる
- 添削が「どの要件が抜けて何点失ったか」まで可視化
- 再提出で改善の軌跡を見られる(1→2回でOKでも進歩がわかる)
💬 体験談(38歳・主婦)
「“要件Aが抜け=▲5点”と数値で言われ、どこを直せば伸びるかが一発で分かった。」
■ 記述特化・主要講座の“質で選ぶ”比較(要点だけ)
| 講座 | 強み | 添削の質ポイント | 目安費用 |
|---|---|---|---|
| アガルート | 記述集中&再提出可 | キーワード表に基づく減点理由が明快 | 3〜5万円 |
| フォーサイト | スマホ提出OK | 音声講評+採点観点の言語化 | 2〜4万円 |
| 資格スクエア | 実務家講師の視点 | 要件漏れの実務影響まで指摘 | 4〜6万円 |
※ 記述対策を主眼にするなら、添削なしプランは除外(講義のみは“言い換え力”が鍛えにくい)。

いつから始める?——開始タイミングと週1メニュー
- 開始時期:民法の基礎インプットが終わったら即(遅くとも学習4ヶ月目)
- 週1ルーティン(60〜90分)
- 択一→60字言い換え×3題(20分)
- 鉄板論点の記述1題を本番時間で(15分)
- 自己採点→キーワード突合(10分)
- 添削返却の反映→再提出(15分)
- 危険知識カード3枚作成(10分)
KPI(毎週記録)
- 迷い正解の件数:10件→5件→3件へ
- 60字テンプレで2分以内に骨組み作成
- 鉄板10論点の再テスト正答率80%
よくある失敗と即修正のコツ
- × 模範解答の丸暗記 → ◯ 60字に“圧縮・要約”
- × 長文で飾る → ◯ 名詞列(処分性・適格・期間)で要件を置く
- × 択一と記述を分けて勉強 → ◯ 択一→記述言い換えのワンセット
💬 体験談(46歳・総務)
「“名詞で並べる”だけで、文章が短く・強くなった。字数管理が一気にラクに。」
まとめ:記述は“労力”ではなく“戦略”で点を積む
- テンプレ(設問要求→要件→結論/40〜60字)を身体に入れる
- 鉄板10論点に集中し、択一→記述の言い換えを毎日3題
- 添削は“質”重視で、減点理由を数値で把握し、72時間でリカバリ
👉 最初の一歩は今日の択一1問を、60字で言い換えること。
「言い換えた回数=記述の得点」です。
社会人の行政書士試験の勉強法はこちらの記事をご覧ください。

🔗 関連記事(内部リンク)
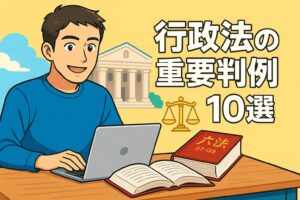


🛍️ おすすめ通信講座
迷ったら「無料体験の添削サンプル」を必ず取り寄せ、
採点基準(キーワード表)を見せてくれるかで比較しましょう。

コメント