「行政法の判例が覚えきれない…」
そんな悩みを抱えていませんか?
行政書士試験では、行政法が配点の約半分を占めます。その中でも判例知識は毎年2〜4問出題される超重要テーマ。
しかし、数百件ある判例をすべて覚えるのは現実的ではありません。
30〜40代の社会人受験生にとって大事なのは、出る判例だけを、規範(判断基準)まで理解して覚えることです。
この記事では、行政書士試験で頻出の重要判例10選と、効率的に覚えるコツ・記述式で使える書き方を紹介します。
行政書士試験の勉強法を知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

1. 行政法判例の出題傾向と狙われ方
出題の特徴
- 択一式で毎年2〜4問出題
- 記述式でも行政法判例は頻出
- 「古くても重要」な判例が中心(最新判例は出にくい)
出題形式と学習ポイント
| 出題形式 | 内容 | 学習ポイント |
|---|---|---|
| 択一式 | 判例の正誤判断 | 判旨の「判断理由(規範)」を覚える |
| 記述式 | 事例に判例理論を適用 | 結論だけでなくなぜそうなるかを60字で書けるようにする |
2. 行政書士試験で覚えるべき重要判例10選(規範つき)
| 判例 | 主な論点 | 試験で狙われる規範(判断基準) |
|---|---|---|
| 朝日訴訟 | 生存権・行政裁量 | 「生活水準の決定は国の広い裁量に委ねられるが、著しく不合理なら違憲」 |
| 薬事法距離制限事件 | 営業の自由 | 「公共の福祉のために必要・合理的な範囲の制限は合憲」 |
| 小売市場事件 | 許可制と営業の自由 | 「目的と手段に実質的関連性があるか」で合憲性を判断(社会的制約説) |
| 公安条例事件 | 表現の自由と許可制 | 「原則禁止・例外許可の制度は事前抑制であり、必要最小限度でなければ違憲」 |
| 北方ジャーナル事件 | 出版の事前抑制 | 「事前抑制は原則禁止。ただし、重大かつ明白な危険がある場合のみ許される」 |
| 行政行為の取消判例 | 無効と取消しの区別 | 「重大かつ明白な瑕疵があるときのみ無効」 |
| 行政裁量の逸脱・濫用 | 行政行為の違法性 | 「裁量権を逸脱・濫用した場合に限り違法」 |
| 国家賠償法1条 | 公権力の違法行使 | 「公務員が職務上違法に国民に損害を与えた場合、国が賠償責任を負う」 |
| 国家賠償法2条 | 公物の設置・管理の瑕疵 | 「通常有すべき安全性を欠いたとき、国に賠償責任がある」 |
| 国会議員定数不均衡訴訟 | 一票の格差 | 「著しい不平等は憲法14条違反となるが、是正に一定の猶予を認める」 |

3. 記述式で狙われるポイントと60字テンプレ
行政法の記述式では、「判例名」ではなく判例の考え方(規範)を自分の言葉で書けるかが問われます。
記述テンプレ(60字目安)
【事例→規範→結論】の順で書く
例:朝日訴訟
「生活保護水準の決定は行政の裁量に委ねられるが、著しく不合理なら違憲となる。」
例:北方ジャーナル事件
「出版物の事前抑制は原則として許されず、重大かつ明白な危険がある場合にのみ例外的に許される。」
👉 「合憲」「違憲」より、“なぜそう判断されたのか”を一文で説明できるようにするのがコツです。
4. 社会人向け・効率的な判例学習法
時間のない人ほど“構造化して覚える”
ステップ①:判例カード4分割法
- 判例名
- 事案の図(人・行政・行為)
- 判旨(結論)
- 規範(なぜそうなったのか)
ポイント:判旨と規範を別々に書くことで理解が深まります。
ステップ②:条文とセットで読む
- 「国家賠償法1条」を読んだら → すぐ「国家賠償法1条判例」を確認
- 「行政行為」学習中なら → 「取消・無効」関連判例を同時に復習
ステップ③:AI活用で効率化
- AIに「判例名+判旨を3行で要約して」と依頼
- その3行を自分の言葉で1行に言い換える
→ これを1日2件やるだけで、1か月で60件整理できます。
5. 実際に使える学習スケジュール例
| 時間帯 | 内容 | 所要時間 |
|---|---|---|
| 朝(通勤) | 判例カード1枚を音読・AI要約 | 15分 |
| 夜 | 判例図+記述テンプレで60字練習 | 45分 |
| 休日 | 条文+判例のセット学習+模試演習 | 2〜3時間 |
忙しい社会人でも「1日1判例×30日」で行政法の基礎が固まります。
6. 体験談(リアルな声)
体験談①:会社員(38歳・初学者)
「条文だけ読んでもピンと来なかったけど、判例カードを作って“なぜその結論なのか”を一言で書くようにしたら理解が深まりました。AI要約→自分の言葉言い換えがめちゃくちゃ時短でした。」
体験談②:パート主婦(41歳・再チャレンジ)
「記述が苦手でしたが、60字テンプレに“規範”を入れる練習を繰り返したら本試験でスラスラ書けました。『北方ジャーナル事件』の“原則禁止・例外許可”をそのまま使えたのが嬉しかったです。」
7. 関連記事



8. おすすめ通信講座|判例も「理解して書ける」段階へ
アガルート行政書士講座(おすすめ)
- 判例・条文・記述を一体で学べるカリキュラム
- 記述式60字添削+質問制度ありで理解が定着
- 忙しい社会人でも「通勤1時間」で進められる講義設計

(参考)他講座の特徴
- フォーサイト:フルカラーでビジュアル理解に強い
- 資格スクエア:講義が分かりやすくAIサポートが充実
- スタディング:スマホでスキマ学習が可能

9. まとめ|「結論」ではなく「理由」を覚える
行政法の判例対策は、単なる暗記ではなく規範(判断基準)を理解して使えるかが勝負。
忙しい社会人ほど、1日1判例+要約+言い換え+60字練習の流れを固定しましょう。
- 判例カードを1枚作る
- AIに要約してもらう
- 自分の言葉で1行に言い換える
- 60字テンプレで書く
これを続ければ、行政法は「苦手科目」から「得点源」に変わります。
焦らず、毎日1歩ずつ積み重ねていきましょう。
社会人の行政書士試験の勉強法はこちらの記事をご覧ください。

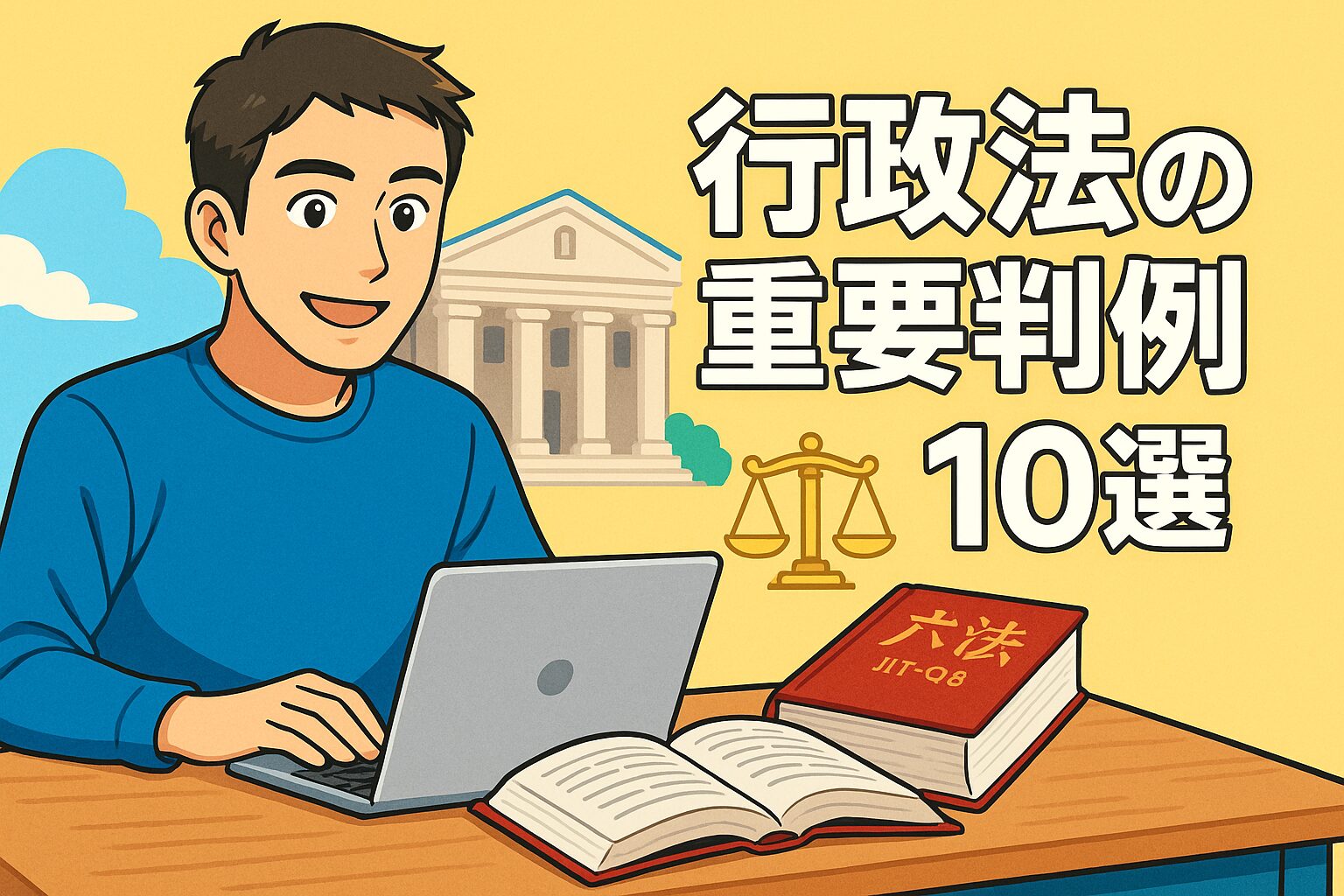
コメント