――夜、ポストから電気代の請求書を取り出した瞬間、胸がざわついた。
「来月もこの調子なら、貯金がまた減る。年金、どうしよう」
仕事はある。でも雇用は不安定。シフトが削られれば収入はすぐ細る。
ふとスマホを開けば、求人は「経験者歓迎」ばかり。履歴書の“職歴の空白”が、面接のたびに突き刺さる。
――このまま50代に入っていくのか。
そんな焦りと一緒に、心の隅にずっとあった願いが顔を出す。
「手に職を。自分の名前で稼げる何かを。」
もし、いまのあなたが次のどれかに当てはまるなら、このページはきっと役に立ちます。
- 「40代後半・非正規(フリーター)からでも、まだ間に合うのか?」
- 「資格は欲しいが、何から手を付ければいいのか分からない」
- 「独学で何度もやり直しては挫折した。もう同じ失敗はしたくない」
- 「合格後の稼ぎ方(実務の入り口)までイメージできない」
読むとわかること
- 40代後半でも届く学習の設計図(“昼を主役”にしたフリーター向けスケジュール)
- 何を捨てるか(行政法・民法に7割、商法・会社法・時事は最低限)
- 忘れにくくする反復の型(翌日・3日・7日ルール/60字テンプレで記述を回す)
- 合格後の現実的ルート:補助者→小さな受任→段階的に独立(初期コスト・注意点つき)
- 「家族の理解」「メンタルの谷」を乗り切る続ける仕組み
体験談:47歳・フリーターSさんのプロフィール
- 雇用:飲食店と倉庫のダブルシフト(週5)
- 学力・法律経験:大学は文系、法律はほぼ初学者
- 学習期間:12か月/総学習時間:約1,050時間
- 合格後:行政書士事務所の補助者として非常勤→半年後に小さく受任を開始
Sさんのひと言
「“若くないから不利”ではなく、“条件が違うだけ”。条件に合ったやり方に変えたら走り切れました。」
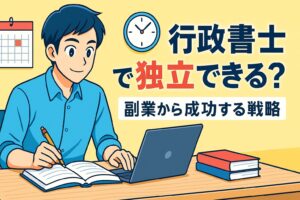
学習の設計図:フリーター向け“昼主役”スケジュール
体力と集中が高い“昼”を重い勉強に、夜は軽作業に回すのがコツです。
| 時間帯 | 学習内容 | ねらい |
|---|---|---|
| 昼(13:00–15:00)90–120分 | 行政法・民法の講義→すぐ基本問題 | 主要科目の理解を深く早く |
| 夕(移動・待機 15–20分×2回) | 一問一答アプリ/条文の穴埋め | 反復で記憶のスキマを埋める |
| 夜(帰宅後 30–45分) | 記述式1問(60字テンプレ)/誤答見直し | 短時間でも“書く”を毎日 |
| 休日(計5–6時間) | 模試2時間+復習2時間+苦手補強1時間 | 模試中心。復習を厚く、量は絞る |
平日は合計2.5〜3時間、休日は5〜6時間。
スマホ=インプット補助/机=アウトプットの役割分担でムダを削ります。

捨てる勇気:40代後半の取捨選択ルール
限られた時間で“合格点”に最短到達するため、配点と出題頻度から逆算します。
- 行政法・民法に学習時間の「7割」
- 条文・判例のインプット→過去問10年×3周が軸
- 商法・会社法は足切り回避の“最低限”
- 頻出論点の○×判定レベルまで。深追いはしない
- 一般知識(時事)に時間をかけすぎない
- 政治・経済・情報は薄めに広く。足切り対策は文章理解で底上げ
- 教材は“1メイン+1補助”に固定
- 迷いが最大の敵。参照先を増やさない
忘れにくくする反復の型(誰でも真似できる)
- “翌日・3日・7日”復習ルール
学んだ範囲を翌日→3日後→7日後に短く復習。各回10〜15分でOK - 60字テンプレで毎日1問“書く”
「論点→結論→根拠」の順で約60字。採点者が拾いやすい語を必ず入れる - 誤答ノートは“スクショ+一行理由”だけ
書き込み地獄にしない。見返せる形を最優先 - 模試は“復習>受験”
2割は模試、8割は模試復習。落とした論点を翌日・3日・7日に再配置
使った道具と“時短のチェックリスト”
通信講座は機能で選ぶと失敗しにくいです。
確認するポイント(ぜんぶスマホで完結できるか)
- 動画の最小単位:10〜15分で区切られているか
- オフライン再生:通勤・待機でギガ消費せず聴けるか
- 演習の動作速度:タップ後すぐ次へ進めるか
- 質問の回答期限(SLA):目安48〜72時間以内か
- 記述の添削回数:最低5回以上あるか
- 法改正フォロー:追加講義や差替テキストが速いか
Sさんはスマホ講義(短尺・オフライン)でインプット、紙テキスト+過去問でアウトプットに寄せ、迷いを消しました。

体験談:Sさんのリアル
「最初の1週間で“やる時間を固定”したのが勝ち筋でした。」
・昼の2時間を毎日カレンダーでブロック
・夜は記述1問だけ(眠くても座れる量)
・模試は2回。復習は翌日2時間固定
「落ち込む日も“ゼロにしない”ことだけ守りました。」
スコアの伸び(例)
- 3か月:択一 120点台 → 6か月:160点台 → 10か月:記述込みで合格点
合格後の“食べ方”:補助者→小さく受任→段階的に独立
いきなり開業ではなく、実務の入口から入ると現実的です。
- 行政書士事務所の補助者
- 期間:3〜6か月(非常勤OK)
- 仕事内容:書類作成補助/役所同行/電子申請の準備
- 探し方:都道府県行政書士会の掲示板/求人サイト/SNS
- 目的:実務の流れと必要機材を掴む
- 小さく受任(副業レベル)
- 得意1分野に絞る(例:建設業許可/古物商許可/相続の書類作成)
- SNS・知人経由で1件目を作る→実績化して紹介につなげる
- 段階的に独立
- 登録費・会費・事務所の設置(自宅の一室で可)など初期コストを試算
- 生活費のクッションを確保(6か月分が理想)
注意メモ
・登録には初期費用や年会費がかかります(地域差あり)
・事務所の設置義務:自宅の一室でも可。ただし賃貸は契約の可否を確認
・副業で収入が出たら住民税の納付方法(自分払い)を検討(自治体運用に差)
・守秘義務・情報管理:紙は鍵付き、データは多要素認証+暗号化
40代後半がつまずきやすい落とし穴と回避策
- 教材を増やしすぎる → メイン1+補助1に固定
- 記述を後回し → 毎日60字1問で“筋トレ”
- 時事に沼る → 一般知識は文章理解重視で足切り回避
- ゼロの日が続く → 15分ルール(どんな日も15分だけ触る)
1週間スタータープラン(そのまま実行OK)
Day1:講座アカウント作成/動画のオフライン設定/カレンダーに昼2時間×7日ブロック
Day2:行政法総論10〜15分×3本 → 一問一答50問
Day3:民法の総論10〜15分×3本 → 一問一答50問
Day4:誤答スクショ整理/翌日・3日・7日の復習リマインド設定
Day5:60字テンプレを覚える → 記述1問
Day6:過去問(行政法)30問/誤答見直し
Day7:ミニ模試(60分)→復習2時間/翌週の範囲決め
関連記事




よくある質問(FAQ)
Q. 40代後半・フリーターでも本当に合格できますか?
A. 可能です。配点の高い科目に集中し、翌日・3日・7日の反復と60字記述を毎日回せば、1年で到達した例があります。
Q. どれくらい勉強すればいい?
A. 目安は800〜1,000時間。不安なら1,000時間を見込み、昼主役のスケジュールで積み上げましょう。
Q. どの講座を選べば?
A. 短尺動画・オフライン・質問の回答期限・記述添削の4点で比較してください。迷ったら無料体験→1週間スターターで試走が確実です。
まとめ:年齢はハンデではなく“設計条件”
- 行政法・民法に7割投下/捨てる勇気
- 翌日・3日・7日の反復と、毎日60字の記述
- 昼主役スケジュールで、合格までの道のりを短縮
- 合格後は補助者→小さく受任→段階的に独立で現実路線
今日の15分が、来年の合格に直結します。
まずは動画を1本、オフライン保存。Day1を終わらせてください。

コメント