「行政書士を目指しているけれど、本当に食べていけるのだろうか?」
「30代・40代から資格を取るなら、どうやってキャリアに活かすのが一番効率的だろう?」
結論は相性抜群です。行政書士は法務・許認可・相続に強く、宅建(宅地建物取引士)は不動産取引・重要事項説明に強い。法務と不動産を横断して扱える人材は希少で、転職・独立・副業のいずれでも評価されます。
本記事は、メリット説明だけで終わりません。夜20分固定でも進む低負荷の行動設計、面接や商談で刺さるA4一枚の見本資料、体験談(数値明記)まで具体化。読了後すぐに今日の3手で動き出せます。
結論
- ダブルライセンスは「法務+不動産」をワンストップで提供できるため、差別化しやすい。
- 30代・40代こそ強い:社会人経験(交渉・管理・顧客対応)を事例化して語れる。
- 夜20分固定+通勤10分の低負荷ルーティンで学習・転職準備・集客を同時並行。
- A4一枚の見本資料で「知識を実務へ落とす力」を可視化→内定率・受注率が上がる。
- 学習順序は宅建→行政書士またはFP3級→宅建→行政書士のどちらでもOK。基礎→専門の流れで挫折を防ぐ。
資格の基本(かんたん比較)
| 資格 | 主な業務 | 活かせる分野 | 学習時間の目安 | 合格率の目安 |
|---|---|---|---|---|
| 行政書士 | 官公署提出書類作成、許認可申請、契約書作成、遺言・相続手続き | 法務・不動産・建設 | 800〜1,000時間 | 約10〜15% |
| 宅建士 | 不動産取引、重要事項説明(独占業務)、契約支援 | 不動産・金融・建設 | 300〜400時間 | 約15〜20% |
読み方:数字は目安です。夜20分×平日+通勤10分で週の合計時間→到達週数を逆算すると現実的な計画になります。
ダブルライセンスのメリット(3点に凝縮)
メリット1:不動産と法務を同時カバー
宅建=不動産の実務/行政書士=法務・書類作成。
売買・相続・許認可が絡む案件で、窓口が一つで済む人として信頼が高まります。
→ 例:売買契約の重説→相続関係書類→名義変更まで一連の流れを設計・進行。
メリット2:転職市場での希少価値
宅建のみ/行政書士のみでも評価されますが、二刀流は稀少。
不動産会社×法務担当/建設会社×許認可+用地など、横断ポジションで刺さりやすい。
メリット3:独立・副業の収益が複線化
行政書士報酬(手続き)+不動産手数料(仲介・紹介)で収益源を2本に。
相続特化や不動産法務特化などニッチ戦略で単価アップも期待できます。
分野別の強み(◎比較表)
| 分野 | 行政書士のみ | 宅建のみ | 行政書士+宅建 |
|---|---|---|---|
| 相続・遺言 | ◎ | △ | ◎◎ |
| 不動産売買 | △ | ◎ | ◎◎ |
| 契約書作成 | ◎ | △ | ◎◎ |
| 建設業許可 | ◎ | △ | ◎◎ |
読み方:行政書士=法務、宅建=不動産。二刀流で意思決定〜実行まで伴走できます。
30代・40代のキャリア戦略(転職/独立)
| 年代 | 戦略 | ポイント |
|---|---|---|
| 30代 | 転職+実務経験の獲得 | 宅建で不動産へ入り、行政書士で契約・法務も担当。A4資料で「運用力」を見せる。 |
| 40代 | 独立・副業の複線化 | 行政書士開業+宅建のコンサルで相続・不動産を一気通貫に。週1相談でテストし安全に拡大。 |
キャリアモデル例
- 不動産営業+行政書士:相続特化の売却支援(遺言→遺産分割→売却)
- 建設会社勤務+行政書士:建設業許可・変更届の内製化で評価UP
- 独立行政書士+宅建士:不動産法務の顧問契約+仲介紹介で収益の底上げ
年収レンジと伸ばし方(目安)
| 資格 | 平均年収レンジ | 伸ばすポイント |
|---|---|---|
| 行政書士のみ | 400〜600万円 | 立ち上がりは案件確保が課題。相続・許認可の型を持つ。 |
| 宅建のみ | 450〜700万円 | 売買営業は歩合で高収入も。行動量×提案の質。 |
| 行政書士+宅建 | 600〜1,000万円 | 相続・不動産のニッチ特化+顧問・紹介で単価を上げる。 |
ポイント:まず実務の土台→不足分野だけ後追い学習がムダなく確実。
学習順序と両立法(低負荷で続く設計)
推奨順序(2案)
- 案A:宅建→行政書士(短期合格→専門へ)
- 案B:FP3級→宅建→行政書士(お金の基礎→不動産→法務で理解が深まる)
ルールは3つだけ
- 夜は20分固定。余力がある日は最大40分。
- ノート作りは禁止。過去問・テキストの余白に1行メモ。
- 通勤10分はアプリ演習。誤答だけブックマーク。
1日の行動(秒・分単位)
- 通勤(片道10分):アプリで過去問○問→誤答をブックマーク。
- 夜20分:
- 0:00–0:30(30秒):ブックマークを開く
- 0:30–10:30(10分):誤答復習(解説を声に出す)
- 10:30–18:30(8分):該当ページの余白に1行メモ(誤答理由・判断のカギ)
- 18:30–20:00(1分30秒):翌日の範囲指定
- 週1回+20分:A4見本資料のチェック項目を3つ追加。
面接・商談で刺さる「A4一枚の見本資料」—即戦力を紙1枚で可視化
見本資料とは:実務で使う前提で作るA4サイズの簡潔な資料。
目的:「知識を実務に落とす力」を1枚で示す。志望動機より説得力があります。
3種類の見本資料(記事にそのまま載せてOK)
- 建設業許可申請フロー(A4)
工程:ヒアリング→必要書類一覧→様式作成→証明書取得→提出→補正対応
欄:担当/期限/提出先(県庁)/進捗□ - 不動産売買・重説チェックリスト(A4)
項目:用途地域/接道/法令制限/権利関係/固定資産税評価/近隣相場 - 相続手続きタイムライン(A4)
流れ:戸籍収集→相続人確定→遺産目録→遺産分割協議→名義変更・解約→申告
作り方(1日20分×3日で完成)
- 1日目:信頼できるテキストの章立てをそのまま項目化。
- 2日目:チェックボックス+空欄(担当・期日・提出先)を付ける。
- 3日目:見直し→印刷(PDF化も)。面接・商談で紙1枚を提示。
面接・商談の一言例
- 「未経験ですが、初週から使える見本資料を作りました。このフローで許可申請を進めます。」
- 「重説チェックはこのA4で漏れなく確認します。」
応募〜受注の行動設計(20分単位)
| 段階 | やること | 成果物 |
|---|---|---|
| 1 | 職務実績を毎日1項目(数字で)書く | 職務経歴書の実績欄 |
| 2 | A4見本資料を3日で仕上げる | A4×1枚(紙+PDF) |
| 3 | 1日1社だけ応募(未経験可×ダブル資格歓迎) | 応募記録(簡単な表) |
| 4 | 想定問答を2問/日作成(計10問) | 60秒プレゼン原稿 |
| 5 | 面接・商談で資料提示→事例→数字で締め | 次回面談・成約へ |
60秒プレゼン(型)
- 結論:「行政書士+宅建として、法務と不動産を一気通貫で支援します。」
- 実例:「許認可→契約→重説の流れをA4フローで運用し、○週間で完了。」
- 運用:「チェックリストで初週から抜け漏れなく進めます。」
- 貢献:「3か月で○件の相談→○件受注の再現を狙います。」
体験談・感想(リアルな声/数値は太字)
体験談①:40代男性/建設会社→行政書士事務所(兼 宅建補助)
「夜20分を守り、週1回+20分で建設業許可のA4フローを作成。面接で提示して内定獲得。入社後3か月で新規許可2件・更新3件。年収は480万→620万円に。」
体験談②:30代後半女性/一般事務→不動産会社・法務補助
「先に宅建、半年後に行政書士。重説チェックA4を見せて2社内定。入社後半年で売買契約14件に関与。誤答の1行メモで用語を素早く吸収できました。」
体験談③:40代男性/保険営業→独立(相続×不動産)
「相続タイムラインA4と不動産売却の流れを作って週1回の相談をSNSで募集。3か月で相談12件、受注6件。初年度年収は700万円。紙1枚が信頼の入口になりました。」
体験談④:30代男性/営業→建設会社・許認可担当
「チェックリスト運用で補正ゼロを継続。夜20分で過去問→余白1行メモを守ったのが効きました。1年で評価昇格。」
感想:「数字→行動→結果」の順で短く語ると、年齢より再現性が評価されます。
よくある質問(FAQ)
Q1. 学習時間が長くて不安です。
A. 夜20分固定+通勤10分の低負荷設計にしてください。ノート作りは禁止、余白に1行メモで十分です。
Q2. どちらを先に取るべき?
A. 短期で勢いをつけたいなら宅建→行政書士。お金の基礎から固めたいならFP3級→宅建→行政書士。どちらも基礎→専門で挫折しにくい順序です。
Q3. 未経験の面接で何を見せる?
A. A4見本資料(建設業許可フロー/重説チェック/相続タイムライン)。「初週の動き」をスケジュールで答えると刺さります。
Q4. 独立は現実的?
A. まずは週1回の相談で副業テスト→反応がよい分野だけ拡大。相続×不動産の特化が有効です。
Q5. 価格の決め方は?
A. 相談料(時間単価)+手続き料(定額)+顧問(月額)の三層構造に。A4資料で作業範囲を見せると納得されやすいです。
低負荷で回す「1週間の型」(例)
| 曜日 | 夜20分の内容 | 補足(+20分するなら) |
|---|---|---|
| 月 | 行政書士:過去問誤答の復習 | A4見本資料の項目整理 |
| 火 | 宅建:重説テーマを1つ復習 | 重要語を1行メモ化 |
| 水 | 行政書士:条文の確認→事例化 | 面接想定問答を2問作成 |
| 木 | 宅建:法令上の制限の弱点潰し | 模擬重説を音読 |
| 金 | 応募または営業DMを1件だけ送る | A4資料の見直し→印刷 |
| 土 | 週の誤答まとめ(10分×2回) | SNSに200〜300字で相談募集 |
| 日 | 休息(または体験談の下書き) | 軽い散歩で記憶定着 |
おすすめの通信講座・転職エージェント
- アガルート:短期合格向け。講義がコンパクトで夜20分学習に合う。(PR)
- フォーサイト:図解が多く、スキマ時間の復習がしやすい。(PR)
- スタディング:スマホ完結で通勤10分の学習がはかどる。(PR)
- 資格スクエア:過去問の傾向分析がしやすいUI。(PR)
- リクルートエージェント:法務・不動産・建設の非公開求人が豊富。(PR)
- doda:未経験可の求人を横断で探しやすい。(PR)
- パソナキャリア:30〜40代のキャリア相談に強い。(PR)
まとめ:今日からの3手(行動がすべて)
- 20分:A4見本資料(建設業許可フロー/重説チェック/相続タイムライン)のタイトル+チェック5項目を書き出す。
- 5分:過去問の誤答に1行メモ(理由と判断のカギ)。
- 5分:エージェント1社だけ登録フォームを送信、または週1相談をSNSに200〜300字で告知。
関連記事
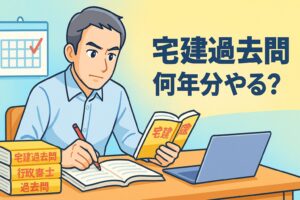

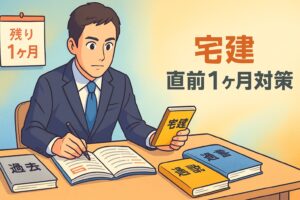


付録:A4一枚の見本資料テンプレ(コピペで使えます)
建設業許可申請フロー(A4)
目的:要件確認〜申請〜補正対応を抜け漏れなく可視化
基本欄:案件名/会社名/担当/期日/提出先
工程(□チェック)
- 要件ヒアリング(経営業務の管理責任者・専任技術者 等)
- 必要書類リスト作成(証明書の発行先・期限)
- 申請様式作成→社内確認
- 添付書類取得→製本→提出
- 補正対応→受理
重説チェックリスト(A4)
目的:重要事項の抜け漏れ防止
- 用途地域/建ぺい率・容積率
- 接道(幅員・方位・間口)
- 法令制限(防火・高度・区画整理)
- 権利関係(抵当権 等)
- 固定資産税評価・公課証明
- 周辺相場・過去成約(出典・日付)
メモ(1行):注意点を太字で
相続手続きタイムライン(A4)
目的:死亡日から完了までの全行程を短時間で俯瞰
- 戸籍収集→相続人確定
- 遺言書の有無確認(検認の要否)
- 遺産目録(預金・不動産・保険)
- 遺産分割協議書作成(合意)
- 名義変更・各種解約(法務局・銀行・保険会社)
メモ(1行):期限・担当・進捗を太字で

コメント