「仕事と家庭の両立で時間がない。自分でも本当に受かるのか?」
——この不安は、30代・40代の受験生なら誰もが抱えるものです。行政書士試験の合格率はおおむね10%前後。一見ハードルは高そうですが、“努力量”ではなく“配点と再現性に基づく戦略”で臨めば、限られた時間でも充分に勝てます。
本記事は、忙しい社会人が最短ルートで合格点に到達するための完全ロードマップです。
配点に基づく学習戦略/時間を空ける仕組み化/その日のうちに定着させる復習テンプレートを、体験談を交えて具体的に解説します。
社会人の行政書士試験の勉強法はこちらの記事をご覧ください。

第1章 行政書士試験の「勝ち筋」を数値でつかむ
合格ラインと配点構造を見える化
| 科目 | 満点 | 目標点(最短ルート) | 重要度のめやす |
|---|---|---|---|
| 行政法 | 112点 | 80点以上(得点源) | ★★★★★ |
| 民法 | 76点 | 50点前後(安定得点) | ★★★★☆ |
| 憲法・商法 | 56点 | 30点程度 | ★★☆☆☆ |
| 一般知識 | 56点 | 30点以上(基準点対策) | ★★★☆☆ |
| 合計 | 300点 | 190点以上を狙う設計(=60%超) |
結論はシンプルです。
行政法+民法で“7割”を取りにいく。
一般知識は「落とさない」=基準点(足切り)クリアを最優先。
この優先順位が、限られた時間でゴールに最速で届くための“配点思考”です。
体験談(38歳・会社員)
「行政法と民法の比重を数字で理解した瞬間、勉強の迷いが消えました。“全部やる”をやめて、“点を取りに行く順番”に切り替えたら、手応えが出るのが早かったです。」
「やらないこと」を先に決める——捨て問のルール
忙しい社会人が合格するには、“戦略的サボり”が不可欠です。次のルールを導入しましょう。
- 過去5年で正答率50%未満の設問は、復習優先度を下げる
- 判例の細部やマイナー条文(例:民法の即時取得の例外など)は「読むだけ」
- 行政法は条文問題 > 判例問題 > 理論問題の順で対策
- 一般知識はまず「文章理解」と「情報通信・個人情報保護」で点を確保。政治・経済は深追いしない
体験談(40歳・主婦)
「“解けた年・解けない年”がはっきり分かれる問題は追いかけないと決めたら、学習が軽くなりました。捨てても行政法と民法で点を積み上げれば合格点は越えられる、と腹落ちしました。」

第2章 12か月ロードマップ(最短で積み上げるステップ設計)
ポイント:「講義 → 小テスト → 図で見直す」を当日中に一往復。短期記憶をその日のうちに長期化します。
ステップ1(1〜3か月):基礎構造の把握——「論点マップ」を作る
- 民法は「総則 → 債権 → 物権」の流れで要件→効果をノート化
- 行政法は「処分 → 不服申立て → 訴訟」を矢印でつないだ図から入る
- 過去問は1周目=論点確認用(正誤よりテーマ把握)
達成基準
- 民法の主要100条を要件→効果で口頭説明できる
- 行政法の条文番号を分野別に3割言える


ステップ2(4〜6か月):過去問2周+弱点マップ
- 2周目は間違えた肢ごとに「条文番号」を必ず書く
- 模試1回で時間配分と得点分布を分析
- 弱点分野を「条文ノート」として1冊に集約
達成基準
- 正答率70%以上の問題群を安定して取れる
- 取消訴訟と不服申立ての構造を自分の言葉で説明できる

ステップ3(7〜9か月):記述・スピード・時間配分を本番仕様に
- 模試2回で90分以内に行政法択一を終える練習
- 記述は「設問要求 → 要件 → 効果 → 結論」の40〜60字テンプレで訓練
- 「正解したが迷った」=危険知識をノート化し、翌週までに潰す
達成基準
- 時間切れゼロ
- 迷って正解を即答レベルへ昇格

ステップ4(10〜12か月):不安定な知識の安定化
- 「正解したが根拠が曖昧」を最優先復習
- 3周目は全肢の理由を声に出して説明(=理解の穴を顕在化)
- 一般知識は「文章理解+情報通信+個人情報保護」を取り切る(政治・経済は深追いしない)
体験談(44歳・メーカー勤務)
「“正解だけど根拠が弱い”問題に赤丸を付けて、毎晩そこだけ確認。本番の迷いが激減しました。」
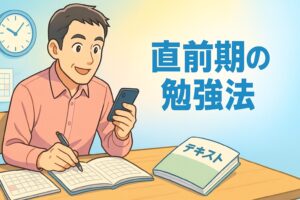
第3章 時間は「作る」ではなく空ける(社会人の時間創出術)
勉強時間は意思でなく仕組みで確保
| 仕組み | 具体例 |
|---|---|
| 家族協力 | 試験日までの期間限定で役割分担を宣言。夕食後の30分は“勉強タイム”として死守 |
| 家事外注 | 週1の家事代行で3時間を創出(月5,000円程度を投資) |
| 仕事調整 | 残業を週1だけ減らす=年間100時間確保 |
| 通勤活用 | 音声講義を1.5倍速で“予習”→夜に一問一答で“再生” |
体験談(41歳・営業)
「朝1時間の早起きより、残業を週1減らす方が効果大。
“投資期間”として家族と合意したのが勝因でした。」
スキマ時間のミニサイクル
- 朝(通勤):講義(20〜25分)を1本
- 昼:小テスト+過去問1問(15〜20分)
- 夜:図で見直し+記述1問の型練習(40〜60分)
推奨ツール例(活用イメージ)
- スタディング行政書士講座:AI復習でスキマ学習を自動最適化
- フォーサイト音声講義:耳学習×倍速再生でインプットを圧縮


第4章 再現性を上げる復習テンプレート(当日往復)
その日の学習を、その日のうちに“往復”させます。
- 講義:1テーマ=20〜30分
- 小テスト:間違いに印を付ける
- 図で見直す:該当ページの図表で関連づけ
- 一言メモ:趣旨を一行で余白に(例「取消訴訟は“処分の取消し”で利益回復」)
この「講義→小テスト→図で見直す」を当日中に完結させると、忘却曲線の“急落”を緩和できます。
第5章 一般知識は基準点対策が正解(深追いしない)
最短設計では、以下の順で取りに行くのが効率的です。
- 文章理解(得点の安定源。短時間で伸ばせる)
- 情報通信・個人情報保護(比較的対策が効きやすい)
- 政治・経済(頻出テーマを要点だけ。深追いはしない)
補助テク
- 文章理解は毎日1題、時間を測って解く(読み癖がつく)
- 情報分野は用語カード(例:「トレーサビリティ」「匿名加工情報」)で朝5分
- 政経はグラフ問題・用語穴埋め中心の薄い問題集で回転数を稼ぐ

第6章 記述対策——「型」で時短&得点を安定化
40〜60字の記述は、型の固定化が命です。
- 設問要求(何を書けと言っている?)
- 要件(A+B+C)
- 効果(どうなる?)
- 結論(一言で締める)
メモ欄には「要件のカタカナ頭文字」だけを書き、清書は日本語で。
添削で粒度(どの程度まで書けば点になるか)を合わせ、毎週2〜3問の固定ノルマで回してください。
体験談(42歳・会社員)
「添削で“減点ポイント”がはっきりわかったので、短文でも点が入る書き方に変えられました。」

第7章 模試の使い方(本番に強い人のチェック項目)
- 事前に時間配分を決めておく(前半:択一/後半:記述)
- 終了直後に再現答案(記憶が新しいうちに)
- 復習は“正解したが迷った”問題から(伸びしろが最も大きい)
- 翌週までに「危険知識」ノートをゼロに

第8章 失点を呼ぶ3つの落とし穴と回避策
- 全部やろうとする
- 対策:配点表を机に貼る。行政法→民法→一般知識(文章理解・情報)の順で死守
- 正解だけど根拠が弱い
- 対策:「根拠あいまい」付箋を貼って週末に集中復習
- 一夜漬けで図が崩れる
- 対策:図の再描写(5分)で体系を再セット
第9章 忙しい人の1日/1週間サンプル計画
1日の例(合計90〜120分)
- 朝通勤:講義1本(20〜25分)
- 昼休み:小テスト+過去問1問(15〜20分)
- 夜:図で見直し+記述1問(40〜60分)
1週間の例
- 月火水:新規講義+小テスト
- 木金:過去問2周目(条文番号を書く)
- 土:模試 or 分野別演習/記述2問
- 日:弱点ノートの整理(危険知識ゼロ化)
第10章 よくある質問(FAQ)
Q. 30代後半・40代でも間に合いますか?
A. 間に合います。毎日90〜120分を9〜12か月続ければ、初学者でも現実的です。**“その日の往復”**を欠かさずに。
Q. 一般知識はどこまでやれば良い?
A. 基準点対策が目的。文章理解+情報通信・個人情報保護を取り切り、政治・経済は深追いしないのが最短です。
Q. 模試の結果が伸びません。
A. 点数より「迷って正解」を即答に変えた数をKPIに。危険知識ノートで翌週ゼロにすれば合計点は上がります。
まとめ:合格は「配点×仕組み×再現性」で決まる
| 要素 | 中身 | 具体策 |
|---|---|---|
| 配点戦略 | 行政法・民法で7割確保/一般知識は基準点死守 | 行政法>民法>一般知識(文章理解・情報) |
| 仕組み化 | 時間は作らず“空ける” | 家族合意・家事外注・残業週1削減・通勤耳学習 |
| 再現性 | “正解したが迷った”を潰す | 危険知識ノート/当日往復/週次ゼロ化 |
体験談(42歳・会社員)
「1年間で約800時間。努力ではなく“設計”。配点と再現性を数字で管理したら、迷いが消えて合格点が見えました。」
今すぐできる3つのアクション
- 配点表を印刷して机に貼る。今日から行政法→民法→一般知識(文章理解・情報)の順で回す
- 過去問1年分だけでいいので、論点マップ(矢印図)を作る
- 無料体験講義で音声×倍速×オフラインの使い勝手を試す(通勤が勉強時間に変わるかを確認)
勉強を始める前に、戦略を設計する。
それが、最短で合格へ向かう唯一の道です。考えています
行政書士試験の勉強法を知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。



コメント