「独学でいける? それとも通信講座?」
42歳の受験生も、最初にぶつかった壁がここでした。
1年目は独学で迷走、2年目に通信講座へ切り替え、3年目に合格(232点)。
結論から言うと、忙しい社会人は“時間を節約する機能があるか”で選ぶのが最短です。
この記事では、独学vs通信講座を「時間コスパ」で徹底比較し、今日から真似できる学習の型まで具体的にお伝えします。
先に「どの講座が自分に合うか」だけ最短で知りたい方は、
比較表つきのまとめ記事が早いです(忙しい人向けに整理しています)。
この記事で分かること
- 独学と通信講座の正直なメリット・デメリット
- 40代が勝つための「捨てる戦略」と「反復の型(翌日・3日・7日)」
- 通信講座を機能ベースで比べるチェックリスト(短尺動画/オフライン/質問の返答期限/記述添削回数)
- 体験談:独学で挫折→通信講座で逆転したビフォーアフター
行政書士試験の基本(ざっくり)
- 受験者:毎年約4〜5万人
- 合格率:10%前後
- 試験:180分/60問/300点満点中180点(6割)
- 科目:憲法/行政法/民法/商法/基礎法学/一般知識
ポイント:行政法・民法が得点の柱。ここを取れるかどうかで勝負が決まります。
独学のリアル:メリット/デメリット
メリット
- 費用が安い(参考書・過去問で1〜2万円程度)
- ペースも教材も自由
- 自分で組み立てるのが好きなら合う
デメリット(ここが痛い)
- 情報の正誤チェックに時間がかかる
- 優先順位を自分で決めるのが難しい(広すぎて迷う)
- モチベ維持がしんどい(相談・添削がない)
- 記述式を後回しにしてしまいがち
独学で最低限そろえる物
- 基本書(例:合格革命など)
- 過去問(10年分以上)
- 予想問題・模試
- 条文・判例の要点集
体験談:私は本屋で立ち読み→比較→また検索…と教材選びだけで数十時間消費。
今思えば、その時間を過去問と記述練習に回せばよかったです。
通信講座のリアル:メリット/デメリット
メリット
- カリキュラムが組まれている(優先順位が見える)
- 短尺動画×アプリ演習で通勤時間が“合格時間”に変わる
- 質問・記述添削で詰まりにくい(学習が止まらない)
- 進捗の見える化でモチベを維持
デメリット
- 費用:5〜15万円程度
- 講座ごとに機能差あり(選び方を間違えると宝の持ち腐れ)
“価格”ではなく“機能”で比べる:時間コスパの判定軸
ここから先は、「どの講座が正解か」ではなく
あなたの生活に合う“機能”で選ぶパートです。
もし「候補を先に絞ってから読みたい」場合は、
主要講座を横並びにした比較表を先に見ておくと迷いません。
| チェック項目 | 重要度 | これがあると起きること |
|---|---|---|
| 短尺動画の最小単位(10〜15分) | ◎ | 朝・通勤に3本回せる→ゼロの日が消える |
| オフライン再生(音声/動画) | ◎ | 地下鉄・圏外でも学べる→毎日の合計時間が安定 |
| AI復習(誤答の自動出題) | ◎ | 翌日・3日・7日の反復を自動化→忘れにくい |
| 質問の回答期限(SLA)明記 | ◎ | 48〜72時間で疑問が解決→学習が止まらない |
| 記述添削の回数・返却速度 | ◎ | 毎日60字テンプレを磨ける→本試験で武器に |
| スマホ操作の軽さ(問題表示・解説) | ○ | ストレスがない→継続しやすい |
| 模試・答練の本番同様運用 | ○ | 時間配分の練習ができ、取りこぼしが減る |
代表的な講座の“相性”の目安
- スタディング:短尺動画+スマホ演習+AI復習→通勤メインの人に
- フォーサイト:フルカラー教材で基礎固め→初学者・理解重視の人に
- アガルート:記述添削が厚い→記述で伸ばしたい人に
- 資格スクエア:IT活用・演習多め→自動で回したい自学型に
上の相性はあくまで目安なので、
最終判断は「価格・機能・サポート」を一覧で見比べるのが確実です。
結論:40代・多忙なら、時間コスパを上げる機能がある通信講座を選んだ方が、合格までの総コスト(時間+年数+機会損失)は下がることが多いです。

40代が勝つための「捨てる戦略」
- 行政法・民法に学習時間の7割を投下
- 商法・会社法:頻出論点に絞り足切り回避ラインまで
- 一般知識:時事は深追いせず、文章理解を確実に取りに行く
→ 点が伸びる場所に資源を集中。これだけで伸びが変わります。
今日から使える「学習の型」
① 反復の型(忘れにくくする)
- 新しく学んだ範囲は、翌日・3日後・7日後に5〜10分だけ再確認
- 誤答はスクショ+一行メモ(なぜ×か)。ノート作りで時間を溶かさない
② 記述の型(毎日60字)
- フォーマットは 〔論点〕→〔結論〕→〔根拠キーワード〕
- 例(行政法・処分性)
「本件通知は法的効果を直接定めず『処分』に当たらない(行訴法3条2)」(57字) - 毎日1問×5分。量より連続日数を重視
③ 1日の型(平日:合計約2.5〜3時間)
- 朝(45分):短尺動画3本+条文音読
- 通勤(45〜60分):AI復習で誤答だけ
- 夜(45〜60分):過去問20問+記述1問(60字)
④ 休日の型(5〜6時間)
- 模試 2時間 → 復習 2時間(受けっぱなし禁止)
- 弱点補強 1時間/記述2問(時間計測)
体験談:独学から通信講座へ切り替えた結果(42歳・会社員/私)
Before(独学)
- 学習時間:年間**〜400時間**
- 勉強法:テキスト+過去問(記述は週末にまとめて→続かず)
- 模試:120点台で頭打ち
After(通信講座+型の導入)
- 学習時間:年間1,000時間超(朝+通勤+夜を固定)
- 勉強法:短尺動画→AI復習→毎日60字
- 模試:180〜200点台へ→本試験232点で合格
感想:「気合い」ではなく“手順”になったのが最大の変化。
学習の“ゼロ日”が消えて、点がじわじわ積み上がりました。
1年合格ロードマップ(行政書士仕様)
| 期間 | 重点 | 具体タスク |
|---|---|---|
| 1〜3か月目 | 土台作り | 短尺動画で全体像→行政法・民法の基本/AI復習を当日運転開始 |
| 4〜6か月目 | アウトプット移行 | 過去問を行政法・民法7割/毎日60字記述スタート |
| 7〜9か月目 | 模試期 | 月1〜2回の模試→復習2時間で原因タグ付け(知識・読み違い・配分) |
| 10〜12か月目 | 直前仕上げ | 予想問題→ミス領域だけ翌日・3日・7日に投げる/文章理解で足切り回避 |
独学が向く人/通信講座が向く人(決め方)
独学が合う人
- 情報の取捨選択が得意(科目の優先順位を自分で決められる)
- スケジュールや進捗を自分で設計・管理するのが苦にならない
- 低コスト最重視(時間はかかってもOK)
通信講座が合う人(多くの30〜40代はこちら)
- 通勤や朝の短時間を積み上げたい
- 反復や質問を自動化して迷いをなくしたい
- 最短で合格し、浪人年数という“見えないコスト”を抑えたい
迷ったら、通信講座の無料体験で“短尺・オフライン・AI復習・質問の返答期限”をチェックしてから決めてOK。
よくある質問(FAQ)
Q. 独学でも本当に受かる?
A. 受かります。ただし40代は時間が最も貴重。計画と反復を自動化できる通信講座の方が合格までの総コストは下がることが多いです。
Q. どの講座が最強?
A. 人によります。“機能”で選ぶのが外れにくいです。短尺・オフライン・AI復習・質問SLA・記述添削の5点で比較してください。
Q. 記述が苦手…
A. 毎日60字×1問でOK。論点→結論→根拠の順でテンプレ化。添削で癖を修正すれば、数週間で形になります。
関連記事



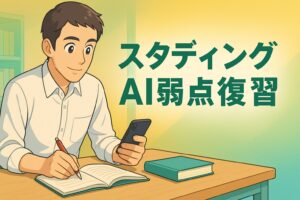
まとめ:結局どっちがいい?
- 独学=費用は安いが、時間の設計と反復の管理を自分でやる必要あり
- 通信講座=費用はかかるが、短尺・オフライン・AI復習・質問SLA・記述添削など、時間を節約する機能で合格までを短縮できる
40代・多忙なら、“機能で選ぶ通信講座”が現実解。
「じゃあ結局どれが合う?」を最短で決めたい方は、
忙しい社会人向けに整理した比較表からどうぞ。▶ 【2025年最新】行政書士おすすめ通信講座5選(比較表つき)はこちら
あわせて読みたい今日、無料体験で短尺動画を1本ダウンロードし、寝る前に翌日・3日・7日の復習リマインダーを入れてください。
そこから、合格への“習慣”が始まります。


コメント