「若い人のほうが有利?」——違います。
40–50代は経験=理解力と計画性=継続力で勝てます。必要なのは“根性”ではなく数値で設計された戦略です。
社会人の行政書士試験の勉強法はこちらの記事をご覧ください。
あわせて読みたい


社会人が働きながら行政書士に合格する方法|時間がない人でもできる勉強術
「仕事が忙しくて勉強時間が取れない…」「30代・40代から挑戦しても行政書士試験に合格できるのだろうか?」 社会人が行政書士を目指すとき、最初にぶつかる壁は時間の…
目次
行政書士試験の概要(超速おさらい)
- 合格ライン:300点中180点(6割)+科目足切り
- 主科目:憲法/行政法/民法/商・会社/一般知識
- 合格率:例年10%前後
🎯 まずは「どこで取るか」を数値で決める(年齢を活かす冷静設計)
| 科目 | 満点の目安 | 最短ターゲット | 戦略 |
|---|---|---|---|
| 行政法 | 112 | 80 | 最優先:手続→救済(不服申立・取消訴訟・執行停止)を一本線で理解 |
| 民法 | 76 | 50 | 次点:要件→効果で条文を口頭化(錯誤/相殺/解除/時効) |
| 一般知識 | 56 | 24–28 | 足切り死守:文章理解3/3+個人情報保護3/4を先に固める |
| 憲法 | 56 | 20–30 | 取りこぼし防止(深追いしない) |
| 商・会社 | 28 | 10–15 | 低投資で拾う。難問は切る |
| 合計 | — | 180+ | 合格点を最短で超える配点設計 |
捨てる基準(時間のムダを断つルール)
- 憲法/商・会社:過去5年で正答率40%未満のテーマには手を出さない
- 一般知識の政治経済:時事冊子のみ(新聞の精読はしない)
体験談(49歳・メーカー)
「“行80・民50・一般24”を手帳に貼ったら、勉強の迷いが消えた。憲法の深追いを切って、週3時間浮きました。」
あわせて読みたい


行政書士試験の難易度と合格率は?初心者でもいける?
――40代からのリスキリングに行政書士は“あり”なのか―― 「40代から行政書士に挑戦するのは無謀?」「合格率が低いって聞くけど、初めての自分でもいける?」 結論から言…
年齢を味方にする3つの戦略
戦略1|“理解力”で勝つ:記憶を技術で固定する
40–50代は暗記より理解が速い。そこで「理解→即アウトプット」で定着率を上げます。
記憶定着のルーティン(30秒×3回転)
- インプット直後30秒:条文を要件→効果で口頭要約
- 昼に30秒:同テーマを一問一答アプリで再生
- 夜に60字:設問要求+要件名詞2–3+結論で短文化(記述テンプレ)
体験談(52歳・総務)
「“朝口頭→昼アプリ→夜60字”にしたら、忘れづらい。週末の模試でも再現できました。」
社会経験を“理解”に変えるコツ
- 民法:ローン・賃貸・相続など自分の経験に当てはめる
- 行政法:手続→救済の業務フローに“職場の手続”を重ねる
- 一般知識:記事は読まず、文章理解の根拠探しに集中
あわせて読みたい


行政法の攻略法|行政書士試験で得点源にする秘訣3選(保存版)
— 40代・多忙な社会人でも“効率重視”で合格点に届く実践メソッド — 「行政法が難しくて、なかなか点数が伸びない」「40代からでも本当に合格できるのだろうか」。こうし…
あわせて読みたい


民法が苦手な人へ|行政書士試験で民法を得意科目に変える3ステップ【初心者向け・低エネルギー版】
「民法は難しい」「事例になると手が止まる」——それ、普通です。ただし民法は、“図にする→型で解く→40字に落とす”の順番にすると、短期間で“得点源”に変えられます。 先…
戦略2|“時間を買い、守る”:週10–15時間を確実に生み出す設計
時間創出の具体アクション
- 家族と学習契約:朝6:00–6:40は勉強、夜は家族時間に“交換”
- 外部化:食材宅配/ロボ掃除/週1家事代行/定期便
- 会社調整:繁忙期2週前から残業の前倒し/昼休み15分を固定学習
1日の型(合計110分・無理なく回す)
- 朝40分:行政法または民法の新規(思考系は朝)
- 通勤30分:耳学習(予習用途)
- 夜40分:危険知識(=迷って正解した問題)を60字で再言語化
週のリスク管理
- 週末に2時間のバッファ(時間的な余裕)を必ず確保
- 予定未達はこのバッファで回収(直前期のバッファは死守)
体験談(46歳・2児の父)
「“朝固定+家族合意+家事外注”で、週12時間を安定確保。メンタルの消耗が激減しました。」
あわせて読みたい


【40代会社員】家庭と仕事の両立で行政書士試験に一発合格した体験記
「子育てや家事に追われて勉強時間がない」「仕事の責任が重く、帰宅後に机に向かう気力が残らない」──そんな悩みを抱えながら行政書士試験に挑戦する30〜40代は少なく…
戦略3|“最小投資・最大回収”:ハイブリッド学習
独学ですでに学習を進めている方は、通信講座は全部見るのではなく、時間を買うピンポイント投資が正解。
ハイブリッドの使い方(最短設計)
- 普段:独学(基本書1冊+過去問+一問一答アプリ)
- 直前2か月:記述添削のみ課金+模試で調整
- 改正対応:法改正レジュメだけ取得(講義は見ない)
3点セット縛り(独学の増殖防止ルール)
- 基本書1冊
- 過去問1冊(直近10年)
- 一問一答アプリ1つ
体験談(50歳・経理)
「独学で伸び悩み→記述添削だけ申込。最小コストで一番伸びる所に投資できました。」

これから学習をスタートする方は、最初から通信講座を受講するのが、最もコスパがいいですよ。
あわせて読みたい




独学で挫折→通信講座で再挑戦!劇的ビフォーアフター【40代でも間に合う“型”を公開】
テキストは買った。最初の1週間は頑張れた。でも残業と家事が重なると、机に向かう気力が消える——。気づけば本は積んだまま、カレンダーの勉強印は空白だらけ。これ、私…
実践テンプレ|これだけやればブレない
過去問“3周”の役割分担
| 周回 | 目的 | 実際にやること |
|---|---|---|
| 1周目 | 論点の地図作り | 設問に論点名を1語メモ |
| 2周目 | 条文接続 | 各誤肢に条文番号を書き込む |
| 3周目 | 説明力 | 全肢の正誤理由を口頭で言う |
危険知識(正解したが根拠が曖昧)は誤答より優先で潰す → 翌朝60字で再言語化。
記述“60字テンプレ”
- 「設問要求」+「要件名詞2–3」+「結論」
- 例:取消訴訟の適法性
→「取消可否は処分性・原告適格・出訴期間で判断。本件は○○で適法。」
あわせて読みたい




記述式はこう書け!行政書士合格者が実践した記述力アップ練習法(改訂版)
「択一式は解けるのに、記述になると手が止まる…」そんな悩みを抱える社会人受験生はとても多いです。 実際、記述式は合否を分ける科目です。2024年度も、記述で10点差…
模試“72時間ループ”
- 当日:誤答(赤)/迷い正解(青)マーキング
- +24h:60字再言語化
- +72h:同テーマを再テスト(口頭OK)
あわせて読みたい




行政書士の過去問はどこまでやるべき?合格者が教える効率的な活用法
「行政書士試験に挑戦しているけれど、過去問ってどこまでやればいいんだろう?」こう悩んでいる30代・40代の社会人受験生は少なくありません。忙しい日々の中で勉強時…
あわせて読みたい




行政書士試験に模試は必要?合格を引き寄せる「戦略的模試活用術」完全ガイド
合格を引き寄せる“戦略的”模試活用術とおすすめ講座【社会人向け完全版】 「行政書士試験は模試を受けるべきか?」——結論、受けるべきです。ただし目的は“実力測定”では…
1年ロードマップ(達成基準つき)
| 期 | 重点 | KPI(達成ライン) |
|---|---|---|
| 1–3か月 | 行政法→民法の骨格 | 民法100条文を30秒で口頭化=70本以上 |
| 4–6か月 | 過去問1周+危険知識抽出 | 危険知識50件可視化/条文番号メモ100% |
| 7–9か月 | 過去問2周+記述 | 記述の骨組み作成2分以内/模試160点 |
| 10–11か月 | 仕上げ | 模試180点/危険知識10件以下 |
体験談(45歳・二度目の挑戦)
「“KPIがある”から、立ち止まらない。合格までの道が可視化されます。」
よくある失敗 → 今すぐの回避策
- 教材を増やす → 3点セット縛りに戻す
- 記述を後回し → 朝15分だけ60字テンプレ固定
- 政治経済に沼る → 時事冊子のみに限定
まとめ|年齢はハンデではなく“装備”です
- 行80+民50+一般24で合格点180を最短突破
- 30秒口頭→一問一答→60字の三段回転で記憶を固定
- 家族契約/外部化/ハイブリッド投資で週10–15時間を“確実に空ける”
👉 今日やる3つ
- 手帳にターゲット(行80・民50・一般24)を書く
- 朝6:00–6:40の学習を家族に宣言
- 過去問1年分を解き、迷って正解した問題に★を付ける
行政書士試験の勉強法を知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
あわせて読みたい




行政書士試験|勉強法ガイド3ステップ【初心者でも最短合格するコツ】
「行政書士試験に挑戦したいけれど、仕事や家庭で忙しく、どうやって勉強を進めたらいいか分からない…」──そう感じる30〜40代の社会人は多いはず。 合格率は例年約10%…
🔗 関連記事
あわせて読みたい




民法が苦手な人必見!「要件→効果」で得点源に変える勉強法3選【行政書士・初心者向け】
「民法が全然頭に入ってこない…」「ボリュームが多すぎてどこから手をつければいいかわからない」 多くの受験生がつまずく理由は、実は量ではなく思考法です。民法は私…
あわせて読みたい




行政書士試験の一般知識対策|足切りを絶対防ぐ効率勉強法【初心者向け】
「行政書士試験の一般知識って、正直どう勉強すればいいのかわからない…」そんな声を、30代・40代の社会人受験生から毎年数多く聞きます。 法律科目に集中するあまり、…
あわせて読みたい




行政書士試験、独学と通信講座どっちがいい?徹底比較【40代・忙しい社会人向けの決め方】
「独学でいける? それとも通信講座?」42歳の受験生も、最初にぶつかった壁がここでした。1年目は独学で迷走、2年目に通信講座へ切り替え、3年目に合格(232点)。結論…
🛍️ おすすめ講座
講座は全部見ないでOK。弱点講義×記述添削×改正レジュメだけ“時間を買う”のが40–50代の最短解です。
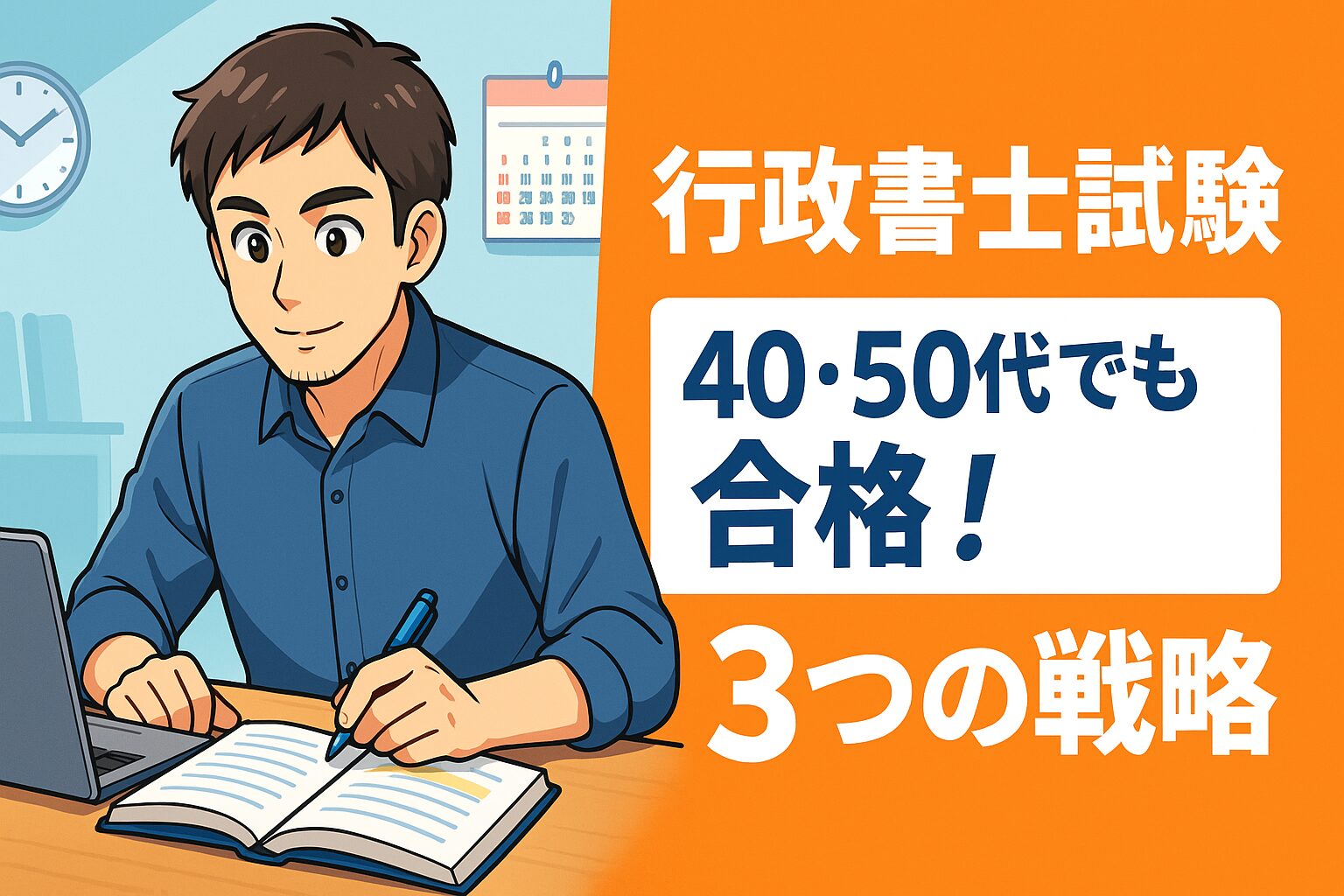
コメント