「範囲が広すぎて、どこから手をつければいいの?」
「法律は初めて。効率よく進めたい。」
そんな30〜40代の社会人向けに、出題範囲の全体地図 → 科目別の勉強法 → “捨てる”優先順位 → 教材の選び方までを、最短合格目線でまとめました。
結論:行政法・民法に時間の7割、他は足切り回避の“最小攻略”でOK。教材は一本化が鉄則です。
▶ 行政書士試験|勉強法ガイド3ステップ【初心者でも最短合格するコツ】はこちら
あわせて読みたい


行政書士試験|勉強法ガイド3ステップ【初心者でも最短合格するコツ】
「行政書士試験に挑戦したいけれど、仕事や家庭で忙しく、どうやって勉強を進めたらいいか分からない…」──そう感じる30〜40代の社会人は多いはず。 合格率は例年約10%…
目次
行政書士試験の全体像
- 試験時間:3時間
- 出題:60問(択一/多肢選択/記述)
- 合格基準:300点満点中180点以上+一部に基準点
出題比率と配点(目安)
| 分野 | 出題数 | 配点 | 比率の目安 |
|---|---|---|---|
| 憲法 | 約5問 | 20点 | 約7% |
| 行政法 | 約19問 | 76点 | 約25% |
| 民法 | 約9問 | 36点 | 約12% |
| 商法・会社法 | 約3問 | 12点 | 約4% |
| 基礎法学 | 約2問 | 8点 | 約3% |
| 一般知識(政治・経済・情報・文章理解など) | 約14問 | 56点 | 約18% |
| 記述式(憲法・行政法・民法) | 3問 | 60点 | 約20% |
▶ 行政書士試験の難易度と合格率は?初心者でもいける?(配点と勝ち筋)はこちら
最短合格の軸
- 行政法+民法+記述で合格点の核を作る
- 一般知識は足切り(14問中6問以上)クリアを最優先
- 商法・会社法/基礎法学は最小攻略で十分
▶ 行政書士、何ヶ月で合格できる?社会人の現実的な最短目安と勝ち方はこちら
科目別:これだけは押さえる勉強法
憲法(人権・統治・改正手続)
- 勉強の柱:人権の判例→統治の仕組み
- やること:
- 重要判例の“結論と理由”を1行で言えるようにする
- 過去問で設問の聞き方に慣れる
- 条文は音声で素読みして馴染ませる
おすすめ教材の要件
- 判例の“何が争点で、裁判所はどう言ったか”が短文で整理されていること
- ○×の根拠が条文・判例レベルで示されること
あわせて読みたい


憲法の条文暗記のコツと頻出条文TOP10【初心者でも覚えられる】
「憲法の条文って数が多すぎて覚えられない…」そんな悩みを抱える人は多いのではないでしょうか。 行政書士試験において、憲法は5〜7問前後が出題され、そのうち2〜3問…
行政法(行政手続・不服審査・訴訟・国家賠償・地方自治)
- 最重要。ここで稼ぐ。
- やること(順序つき)
- 行政手続法/不服審査法:手続の流れを図にする
- 行政事件訴訟法:訴訟類型と要件を表で
- 国家賠償法:要件と判例の型
- 地方自治:条文の全体像を広く薄く
覚え方のコツ
- 「誰が」「いつ」「どの書類で」「どこへ」「不服は何日以内」—穴埋めで言える状態に
- 記述対策は、設問→要件当てはめ→結論の3段で40字に収める練習
教材の要件
- 手続フローチャート/図解が豊富
- 記述の答案骨子が載っている
あわせて読みたい

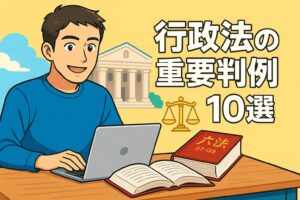
判例対策|覚えるべき重要判例(行政法中心)10選と出題傾向(改訂版)
「行政法の判例が覚えきれない…」そんな悩みを抱えていませんか? 行政書士試験では、行政法は最大の得点源です。その中でも判例知識は毎年2〜4問出題される超重要テー…
民法(契約・物権・債権総論・家族)
- 時間がかかる科目。最初は“厚塗り”禁止
- 1周目の目標:
- 「物権と債権の違い」「要件→効果」の型だけ掴む
- 難所は飛ばしてOK。2周目以降に回収
- 2周目以降:過去問の事例の型を集める(売買解除・時効・相続など)
教材の要件
- 事例で要件→効果が一目で分かる
- 記述式の骨子(要件列挙→当てはめ)が練習できる
あわせて読みたい


民法が苦手な人へ|行政書士試験で民法を得意科目に変える3ステップ【初心者向け・低エネルギー版】
「民法は難しい」「事例になると手が止まる」——それ、普通です。ただし民法は、“図にする→型で解く→40字に落とす”の順番にすると、短期間で“得点源”に変えられます。 先…
商法・会社法(低配点)
- “捨てる勇気”の代表
- やること:直近10年過去問で頻出テーマだけ(機関・株式・設立など)
- やらないこと:細かい制度の周辺知識の深追い
教材の要件
- 過去問の出題頻度マークが明確
- 要点の1ページ要約がある
あわせて読みたい


商法の最短攻略法|捨てずに拾う!出るとこだけ学ぶテクニック(改訂版)
「商法は範囲が広すぎて、どこから手をつけていいかわからない…」そんな悩みはよくあります。結論はシンプル。商法は“捨てる”のではなく“低コストで拾う”科目です。出題…
一般知識(足切り対策が最優先)
- 文章理解(現代文):毎日1問・5分で確実に3問取り切る
- 情報通信・個人情報保護:直近の法改正・白書事項だけを短期暗記
- 政治・経済:高校レベルの総まとめで浅く広く
教材の要件
- 文章理解の解法パターンが見開きで整理
- 情報分野は改正ポイントだけ抜き出し
あわせて読みたい


行政書士試験の一般知識対策|足切りを絶対防ぐ効率勉強法【初心者向け】
「行政書士試験の一般知識って、正直どう勉強すればいいのかわからない…」そんな声を、30代・40代の社会人受験生から毎年数多く聞きます。 法律科目に集中するあまり、…
記述式(3問・60点)
- 配点が重い=“型”で拾える
- 練習法:
- 過去問を40字骨子に要約する訓練
- 答案構成メモ(要件→当てはめ→結論)を15分で作る練習
- 添削があると加速(返却期限が短いほど良い)
教材の要件
- 出題論点の型がテンプレで示される
- 添削の返却期限が明示
あわせて読みたい


記述式対策はこうする!行政書士試験で高得点を狙う勉強法3選【初心者向け】
「択一は何とかなるけど、記述式が怖い…」30〜40代の社会人から本当によく届く声です。 記述は3問×20点=60点。合格者の平均は24点前後と言われ、まさに合否の分水嶺で…
時間配分の“正解”(目安)
- 行政法:民法:その他=4:3:3
- 一般知識は文章理解+情報分野で足切り回避を先に固める
- 商法・会社法/基礎法学は“頻出マーク部分”だけ
やらないことリスト
- 教材を増やす
- 細部を完璧にするまで進まない
- 模試だけ解いて復習しない

やらないことを決めることが、合格のためにはとても重要です。
やらないことリストの1つでもやってしまっている方は、直ちに改めてください。
教材の選び方(一本化の基準)
- 短い講義(10〜20分)×倍速で回せる
- オフライン再生できる(移動中でも止まらない)
- 誤答の自動反復ができる(翌日・3日・7日の復習)
- 質問の回答期限(SLA)がある(停滞しない)
- 記述は答案骨子のテンプレ+添削の返却期限が明示
迷ったら、「地下鉄テスト(オフラインで再生できるか)」と「翌朝テスト(誤答が自動で出るか)」の2点だけ確認。
おすすめ
▶ 【比較表】行政書士おすすめ通信講座5選(2025年最新版)はこちら
- 編集方針:本文で示した「止まらない機能」を満たす教材のみ推奨します。
- おすすめ講座(PR):アガルート行政書士講座
- 短尺講義/倍速/オフライン対応
- 質問の回答期限が明確・記述添削の返却期限あり(プランによる)
- 記述の答案骨子テンプレが実務的で、40字にまとめやすい
- → 短期合格の“出力重視”運用に合う
※各社の仕様は年度・プランで変わるため、申込前に公式でご確認ください。
あわせて読みたい




【40代からの挑戦を応援】アガルート行政書士講座で一発合格を目指せる理由(評判・口コミ・学習法を完…
「仕事や家庭で忙しいけれど、資格を取りたい」「40代から行政書士試験に挑戦するのは遅いのでは?」——そんな不安は、正しい学習法と道具選びで乗り越えられます。行政…
体験談(モデルケース/第三者)
- ケースA:43歳・営業(初学)
- 行政法は手続の流れを図、民法は事例の型で回す
- 平日:音声15分×2/一問一答10分/夜は過去問20分
- 記述は要件→当てはめ→結論の骨子だけ毎日1題
- 7か月で合格
- ケースB:38歳・事務(子育て中)
- 一般知識は文章理解を毎日1問+情報分野の改正だけ
- 商法・会社法は頻出論点だけに限定
- 足切り回避→記述強化の順で点が安定
よくある質問
Q. 教材は何冊必要?
A. テキスト1冊+過去問1冊(または講座内セット)+記述対策で十分です。
Q. 一般知識が不安です。
A. 文章理解を毎日5分で確実に3問。情報分野は改正ポイントだけ短期暗記。これで足切りは現実的に回避できます。
Q. 商法・会社法はどこまで?
A. 直近10年の頻出論点だけ。全範囲の深追いは不要です。
関連記事
あわせて読みたい




【失敗しない】【2025年最新】行政書士おすすめ通信講座5選|比較表&選び方を徹底解説!
「行政書士の通信講座、種類が多すぎて選べない…」そう感じている方は多いはず。特に30代・40代の社会人は、仕事や家庭と両立しながら法律の基礎から学ぶ負荷が大きく、…
あわせて読みたい




「挫折しない講座」とは?合格者が選ぶ、継続しやすい行政書士講座
「忙しくて続かない」「本を買っただけで止まった」——30〜40代の最大の壁は、難しさより継続です。本記事は、読者の“決めきれない”負担を減らすために、講座選びをたっ…
あわせて読みたい




行政書士試験のスキマ時間活用法【働きながら合格する勉強術】
「仕事が忙しくて勉強時間が取れない…」「家事や育児の合間で、ほんの少ししか勉強できない…」 30代・40代の社会人受験生に共通する悩みです。行政書士試験は、合格に80…
あわせて読みたい




【初心者向け】行政書士、何ヶ月で合格できる?
社会人が知るべき“現実的な最短”の目安と勝ち方(体験談つき) 「合格までに何ヶ月かかる?」30〜40代の社会人にとって、一番の不安は“時間”。結論から言うと、必要学習…
まとめ:範囲は広い。だから「捨てる」と「型」で勝つ
- 行政法・民法に7割、一般知識は足切り回避を先に固める
- 商法・会社法/基礎法学は最小攻略
- 教材は一本化し、「短尺・オフライン・自動反復・質問期限」で止まらない設計に
👉 今日の一歩:行政法の手続フローを1枚の図にする→すぐ過去問1セット。
“完璧”ではなく“前進”。それが最短合格の合言葉です。

コメント