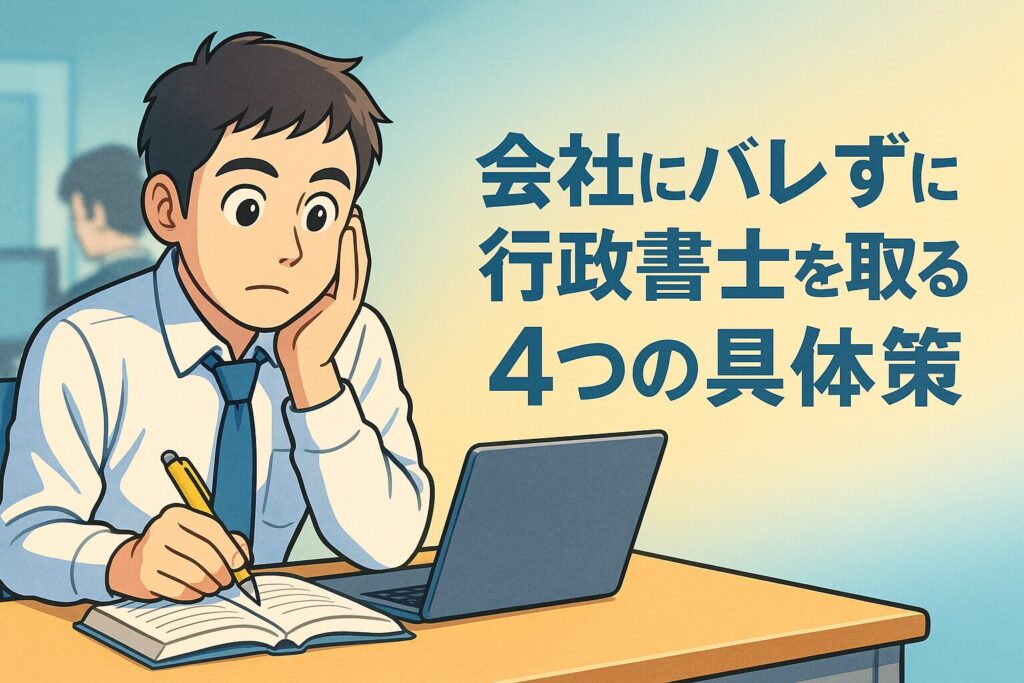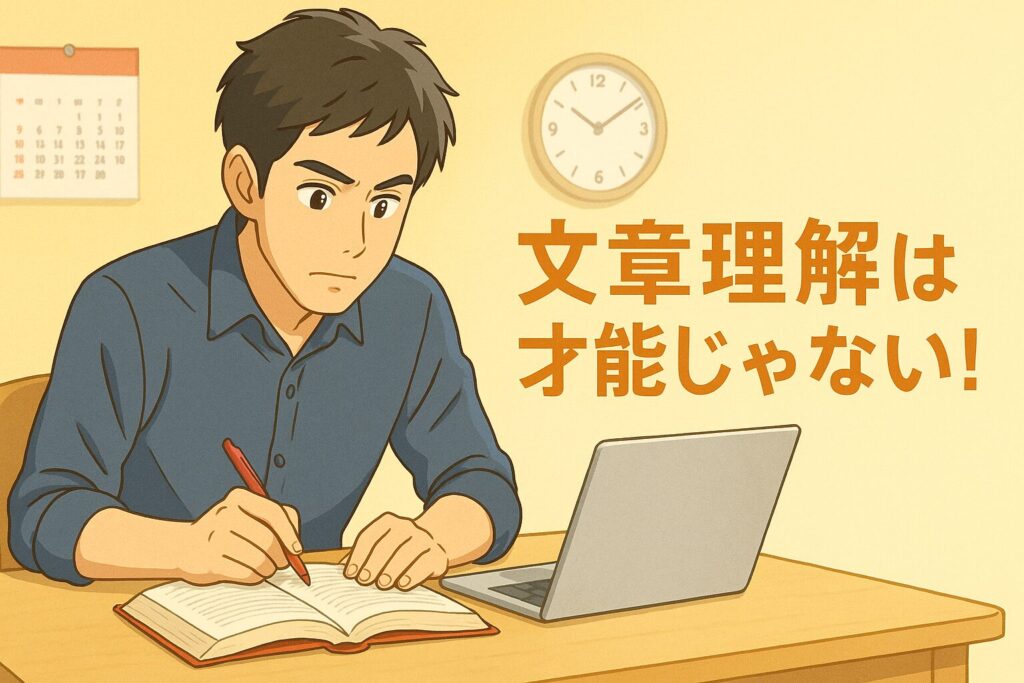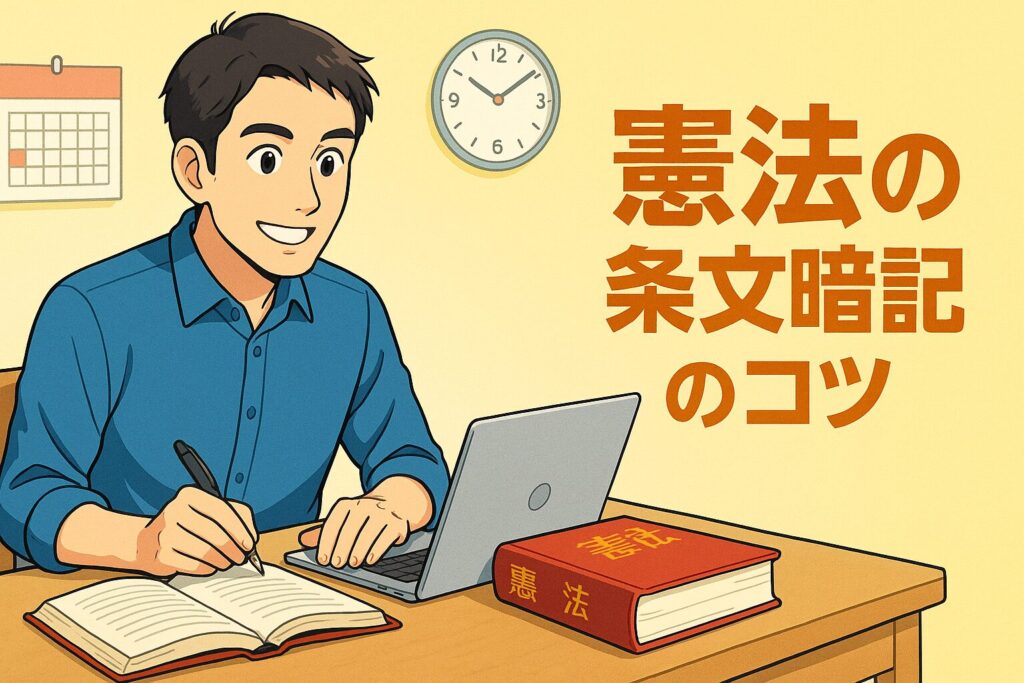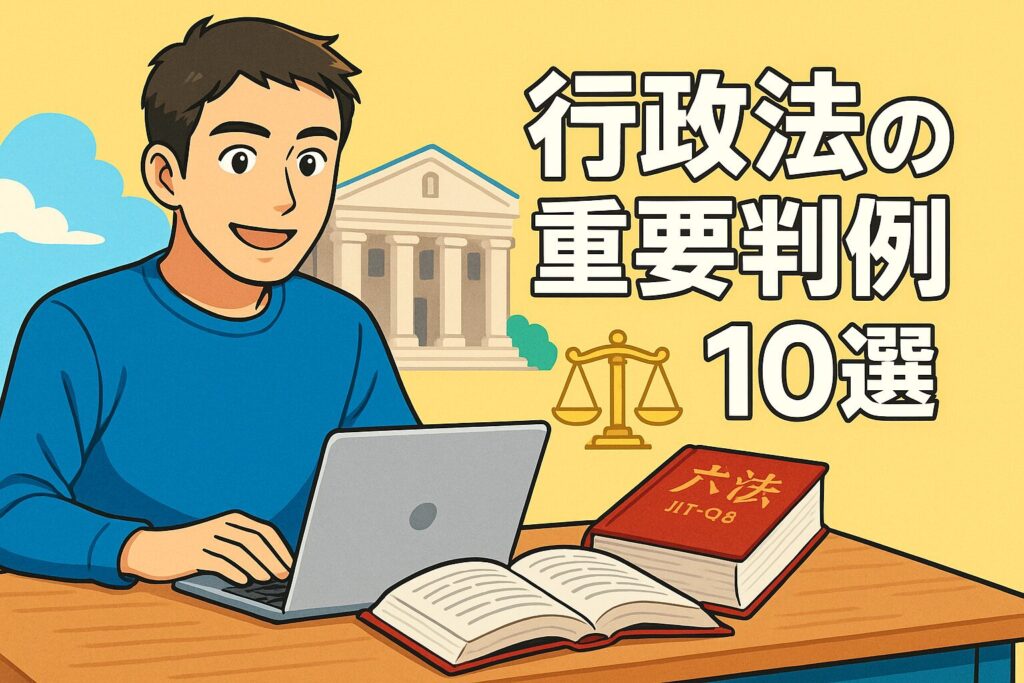行政書士試験の勉強法– category –
-

会社にバレずに行政書士の資格を取る4つの具体策と注意点【合格までは静かに、登録は戦略的に】
「行政書士の資格を取りたいけれど、会社に知られるのは避けたい…」30代・40代の社会人にとって、キャリアの幅を広げる資格取得は魅力的な一方で、「副業禁止規定」や「同僚の目」が気になって一歩踏み出せない人も多いですよね。 結論から言うと、勉強か... -

記述式はこう書け!行政書士合格者が実践した記述力アップ練習法(改訂版)
「択一式は解けるのに、記述になると手が止まる…」そんな悩みを抱える社会人受験生はとても多いです。 実際、記述式は合否を分ける科目です。2024年度も、記述で10点差が合否を分けたというデータがあります。つまり、「書ける」かどうかが合格ラインを決... -

行政書士試験「多肢選択式」の傾向と勉強法|出題意図を読み解く方法(改訂版)
「多肢選択式は長文がキツい…」「最後まで集中できない…」——大丈夫。多肢選択式は長文“風”の知識問題です。出題者は、条文や判例から重要な一語(フレーズ)を抜き、“その語を入れられるか”を試しています。つまり、読む力より“空欄を予測する力”が点に直... -

行政書士試験における「五肢択一」の攻略テクニック大全
「知識は入れたのに、選択肢で迷う」「正誤問題に振り回される」——よくある悩みです。五肢択一は知識 × 解き方(技術)で点が安定します。ここでは、形式別の戦い方と科目別の急所、そして時間配分の現実解を示します。 1. 出題の全体像(押さえるべき事実... -

文章理解は才能じゃない!点数を伸ばす読解の型とトレーニング法【行政書士試験対策】
「文章理解が苦手で点が伸びない…」大丈夫。文章理解は才能ではなく“型(決まったやり方)”で伸びます。しかも毎年3問=12点は、練習すれば安定して取りやすい“コスパ最強ゾーン”。ここでは、現代文2問+英文1問を安定して8〜12点に乗せるための最短ルート... -

基礎知識:個人情報保護法はどう出る?出題パターンと対策法3選【行政書士試験】
「行政書士試験で個人情報保護法ってよく出るらしいけど、どう勉強すればいいの?」——そんな悩み、この記事で解決します。 結論:この科目は「定義」「事業者の義務」「改正点(構造の変化)」に集中すれば、短時間で確実に点が取れる分野です。特に直近改... -

商法の最短攻略法|捨てずに拾う!出るとこだけ学ぶテクニック(改訂版)
「商法は範囲が広すぎて、どこから手をつけていいかわからない…」そんな悩みはよくあります。結論はシンプル。商法は“捨てる”のではなく“低コストで拾う”科目です。出題は毎年2〜3問。ここを短時間で確実に1〜2問取れれば、総合点が安定します。 1) 方針:... -

憲法の条文暗記のコツと頻出条文TOP10【初心者でも覚えられる】
「憲法の条文って数が多すぎて覚えられない…」そんな悩みを抱える人は多いのではないでしょうか。 行政書士試験において、憲法は5〜7問前後が出題され、そのうち2〜3問は条文知識だけで取れる問題です。判例問題と違い、条文暗記は“やった分だけ確実に点に... -

行政法の判例対策|覚えるべき重要判例10選と出題傾向(改訂版)
「行政法の判例が覚えきれない…」そんな悩みを抱えていませんか? 行政書士試験では、行政法が配点の約半分を占めます。その中でも判例知識は毎年2〜4問出題される超重要テーマ。しかし、数百件ある判例をすべて覚えるのは現実的ではありません。 30〜40代... -

民法の時効制度をマスターする!行政書士試験頻出テーマ完全ガイド(改訂版)
「民法の時効制度って難しそうで覚えきれない」。そんな人に向けて、“覚える順番”と“書く手順”をハッキリさせます。30〜40代の社会人でも、毎日60〜90分で回せる現実的なやり方です。 1. まず押さえる“地図”——試験で問われるのはここ 頻出:消滅時効(起算...